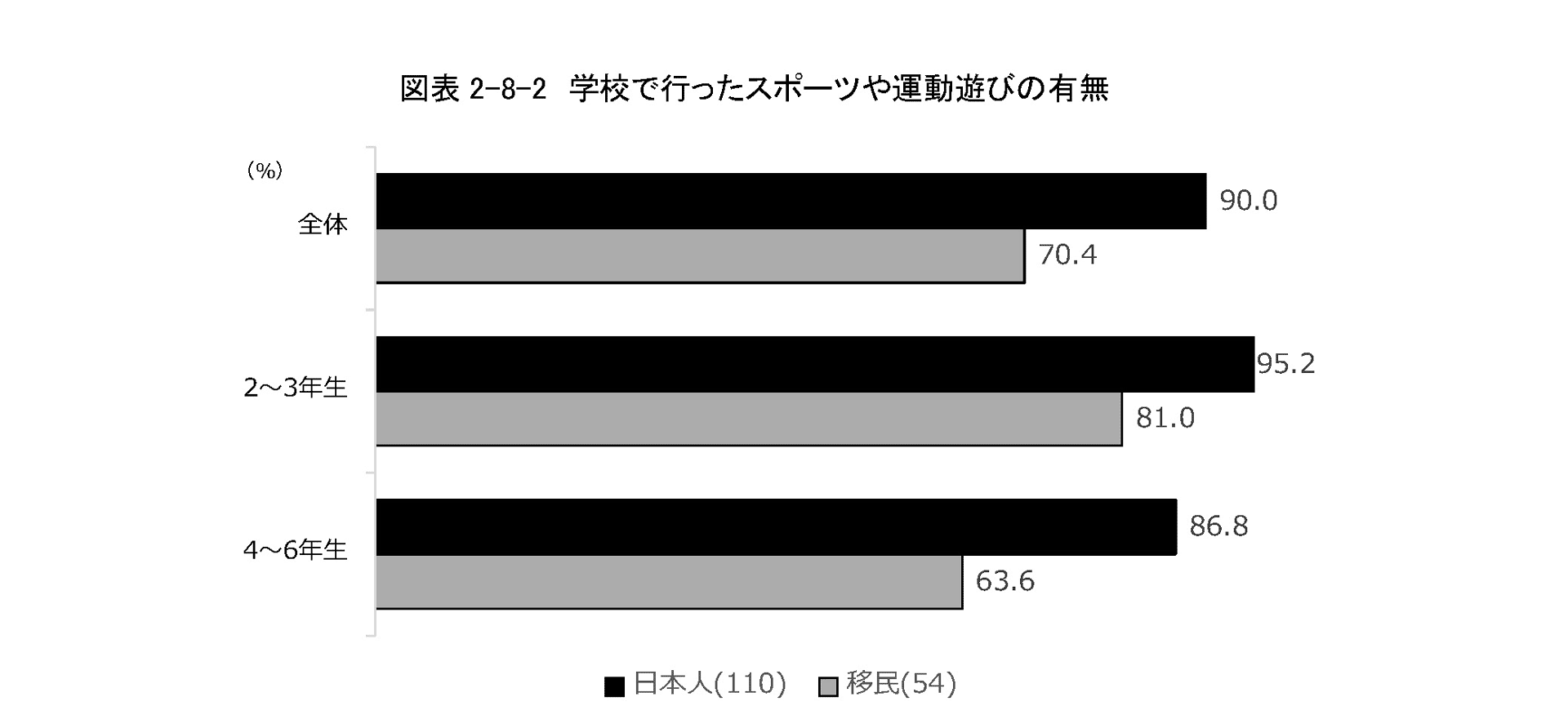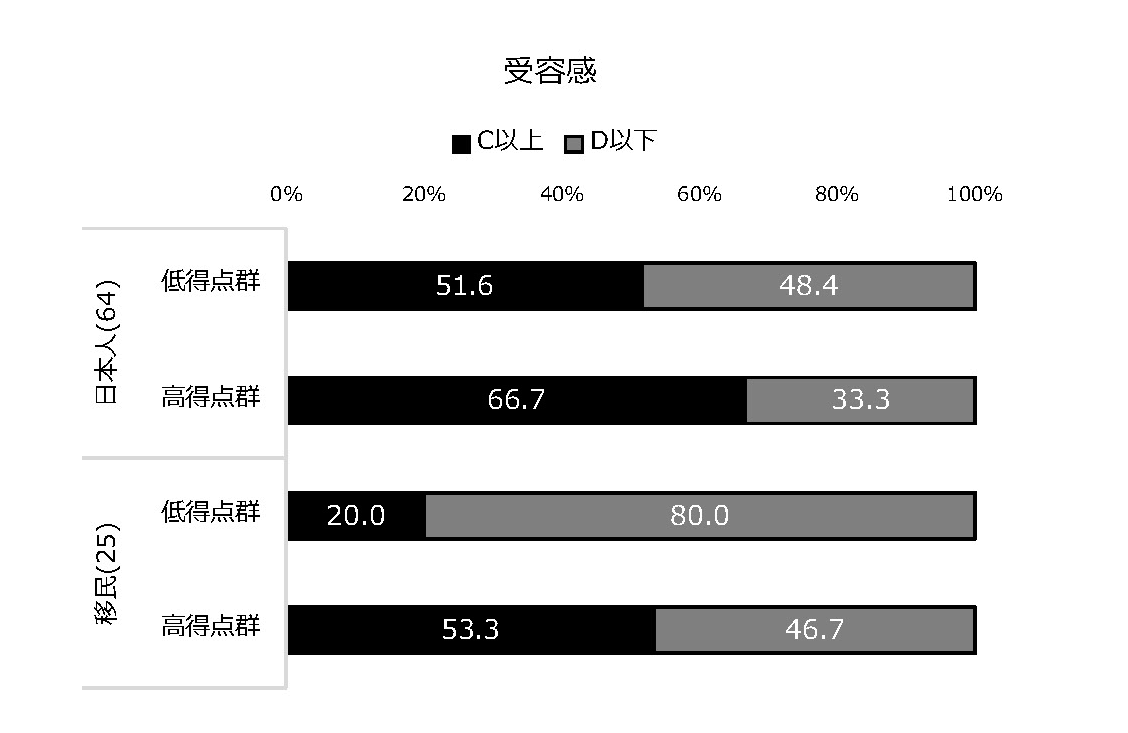笹川スポーツ財団(SSF)では、2023年10月に東京23区内の公立A小学校(以下A小学校)の1年生~6年生の児童および保護者を対象とし、「国際化が進む公立小学校における子どもの運動・スポーツ実態調査」を同校との共同事業として実施しました。
調査の結果、これまでほとんど明らかにされてこなかった、外国にルーツのある子どもたち(以下、移民※の児童)の運動・スポーツ実施状況とその課題がみえてきました。現状、移民の児童が多い学校では、日本語でのコミュニケーションが難しい児童や保護者の対応が、各教員に委ねられている状況にあります。今後は移民の児童も含めてすべての子どもたちが、学校内外で楽しくスポーツや運動遊びに取り組めるよう、社会全体での環境整備、課題解決が求められます。
※本調査では、いずれかの保護者(ひとり親の場合も含む)の第一言語が「日本語以外」であるケースを「移民」、すべての保護者(ひとり親の場合も含む)の第一言語が「日本語」の場合を「日本人」として区別していますが、あくまでも本調査による分析上の暫定的な定義として用いています。
主な調査結果
1. 体育の単元では水泳(水遊び・水泳運動)を好む移民の児童が特に多い
体育の各単元の内容について、好きかどうかをたずねたところ、「水泳」は共通して人気が高く、日本人61.8%<移民75.9%と、特に移民で好きな児童が多いことがわかる(図表割愛)。移民には宗教上の理由で水泳の授業が受けられない児童もいるものの、来日してはじめてプールを経験し、楽しむ児童も多いと推察される。一方で「マット運動」(日本人48.2%>移民31.5%、以下同)、「鉄棒」(30.9%>25.9%)、「とび箱」(49.1%>40.7%)といった器械運動の単元では、いずれも日本人より移民の割合が下回り、5~17ポイント程度の差がみられる。器械運動に馴染みのない児童も多く、移民の指導における難しさが浮かび上がる。
2. 日本人と比べて学校でスポーツや運動遊びをしている移民の児童は少ない
児童が調査当時の学年になってから学校の授業以外で行ったスポーツや運動遊びの内容をたずねた。1種目でも行ったか否かで分けて学校でのスポーツ・運動遊びの実施率をみると、日本人90.0%>移民70.4%と、約20ポイントの差がみられた(図表1)。2~3年生と4~6年生に分けて分析すると、2~3年生では日本人95.2%>移民81.0%、4~6年生では86.8%>63.6%となり、高学年になると移民の約4割が校内でスポーツや運動遊びに参加していないことがわかる。
また、ドッジボールやおにごっこは属性による実施率の差が大きく、ドッジボールでは最も実施率の高い日本人男子で81.5%であるのに対して、移民女子は35.0%であった。同様に、おにごっこでは日本人女子73.2%、移民男子では47.1%であった(図表割愛)。
図表1. 学校で行ったスポーツや運動遊びの有無
注1) 学校で行ったスポーツや運動遊びの種目を複数回答でたずね、ひとつでも選択した児童の割合を示している
3. 体力テストにおいて、日本人・移民の児童間で平均値に差のある項目がみられる
体力テスト(「新体力テスト」)の結果をみると、握力と長座体前屈は日本人より移民のスコアが若干高かったが、そのほかの種目では日本人が高かった(図表割愛)。反復横跳び・20mシャトルラン・50m走においては平均値に有意な差がみられ、特に反復横跳びと20mシャトルランには大きな差を認めた。体格や運動経験の違いだけでなく、体力テストのルール理解や慣れの不足も影響していると考えられる。
4. 体力テストの結果と、先生や友だちからほめられる経験との関連がみられる
運動有能感をたずねた項目のうち、「受容感」(「先生が励ましてくれる」「友だちが励ましてくれる」)の得点群別(低得点群、高得点群)に体力テストの総合得点が「C以上」であった割合を比較すると、移民は日本人より低得点群と高得点群の差が大きい傾向が確認された(図表2)。体力テストの結果が低い移民の児童は、前述のとおり体格や運動経験の問題に加え、言語の課題もありテストのルールや意義を十分に理解できていない可能性がある。そのような子どもたちがほめられる経験を十分に積めていない点は、移民の運動・スポーツを考える上で重要な課題といえる。
図表2. 受容感と体力テストの関連