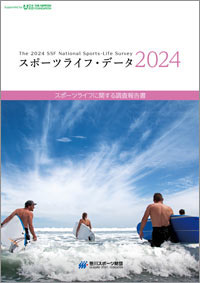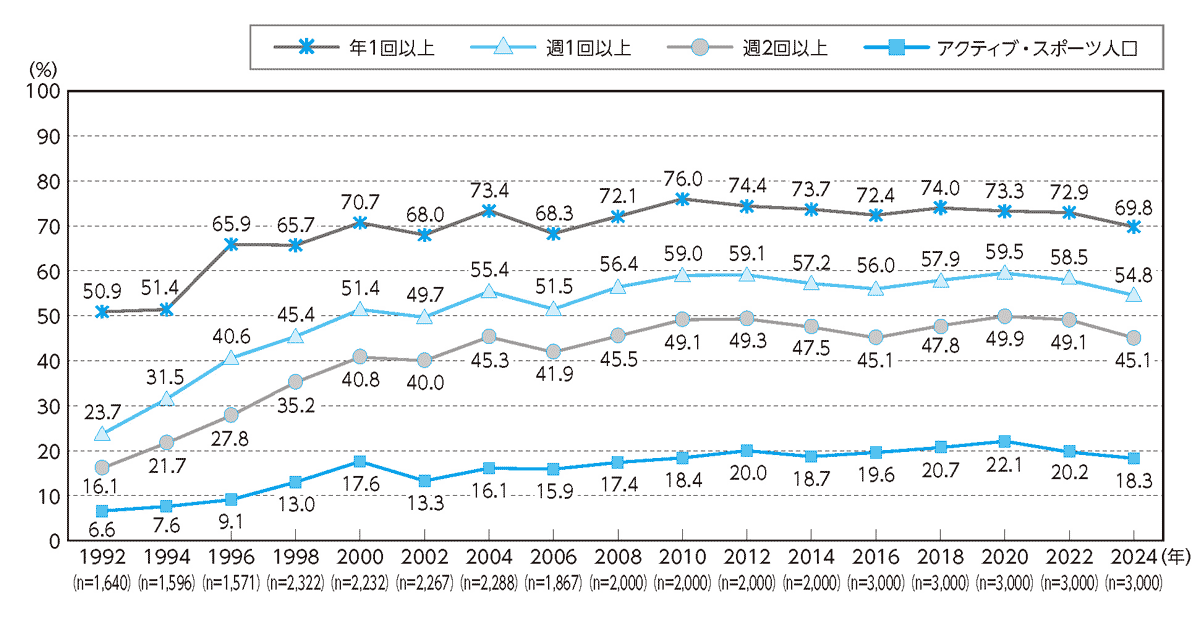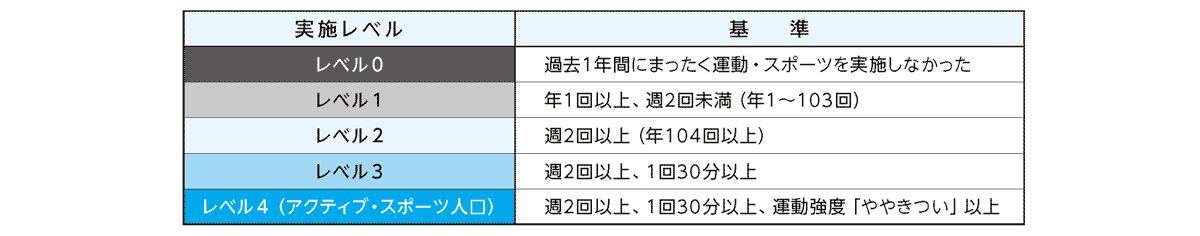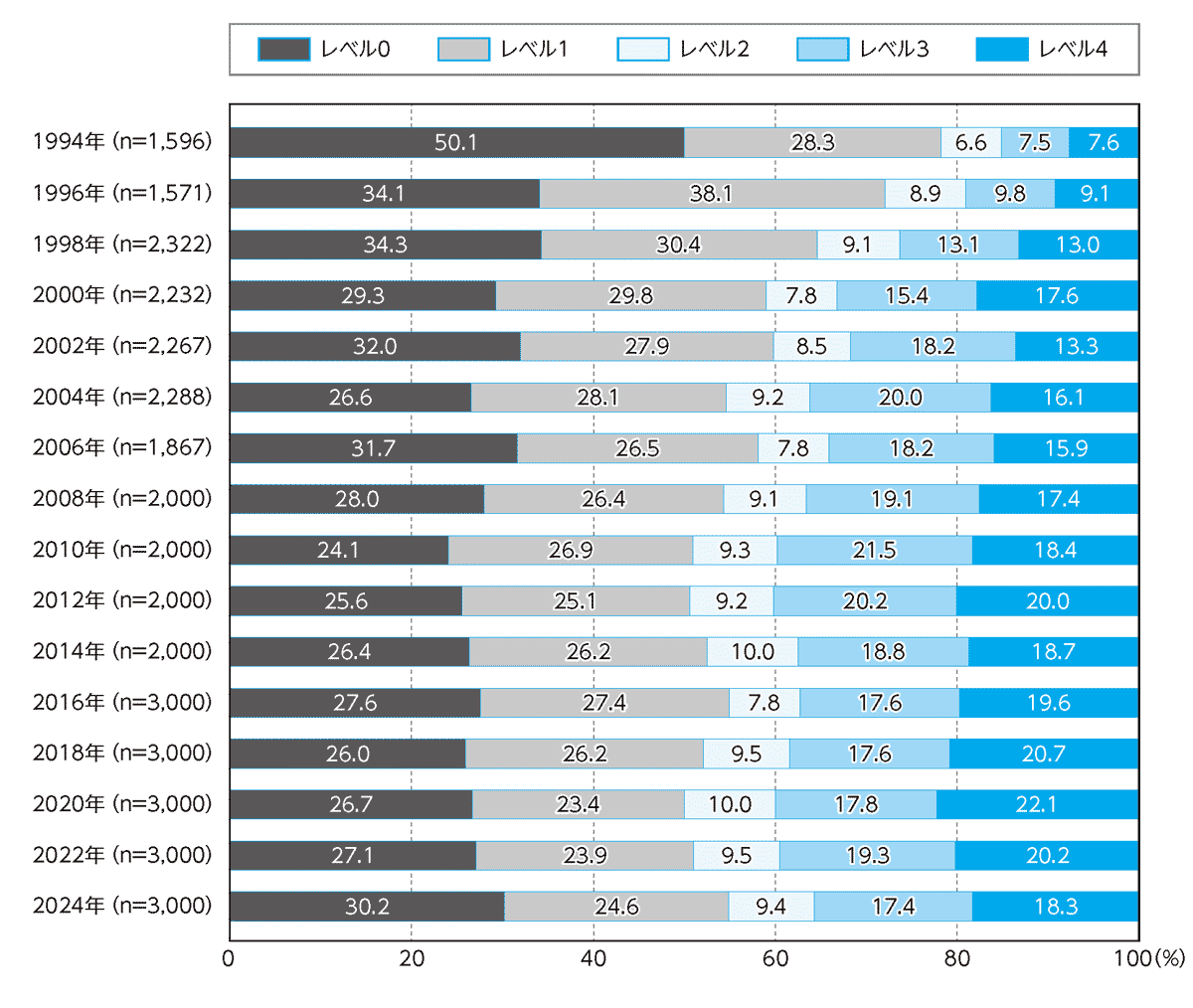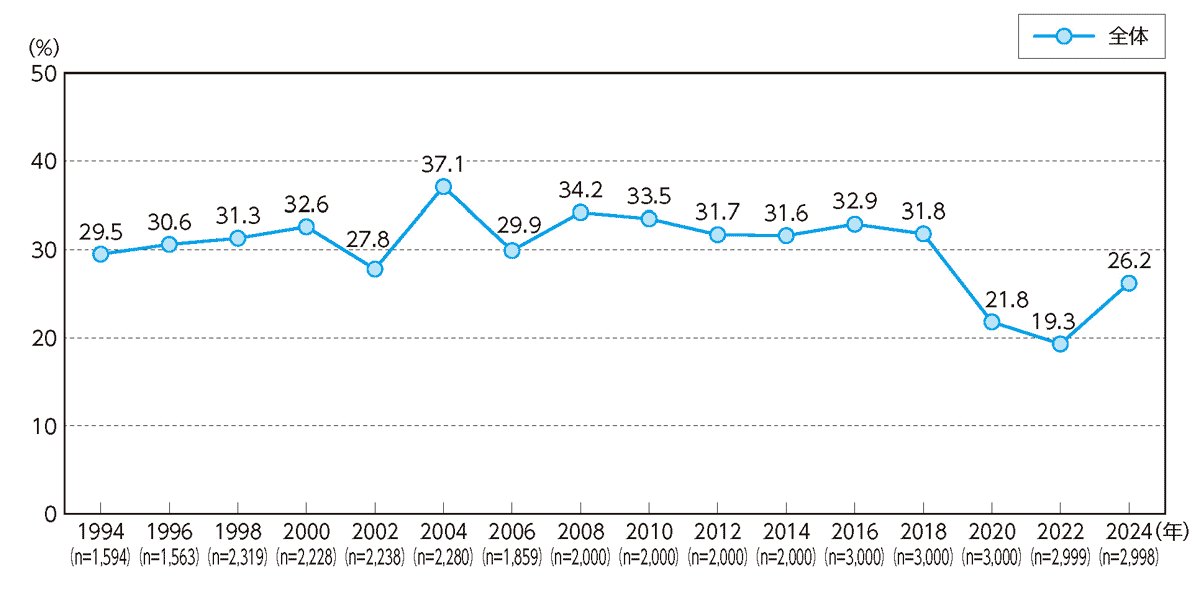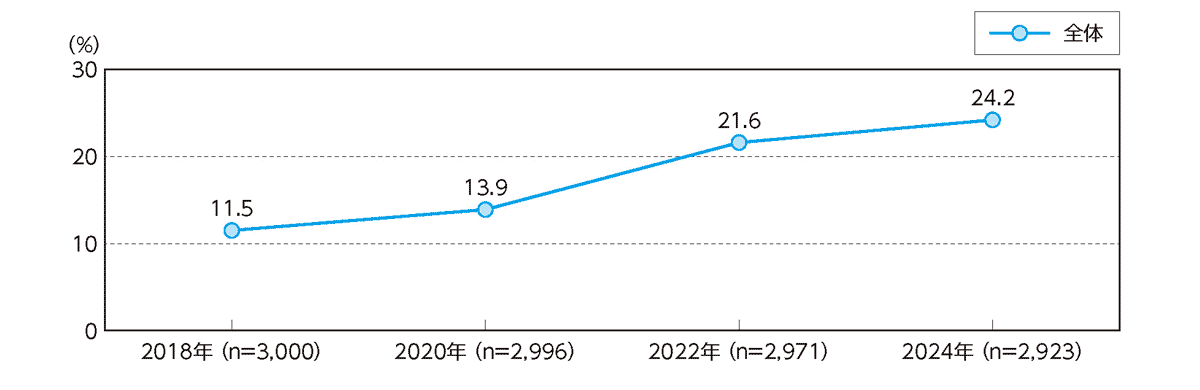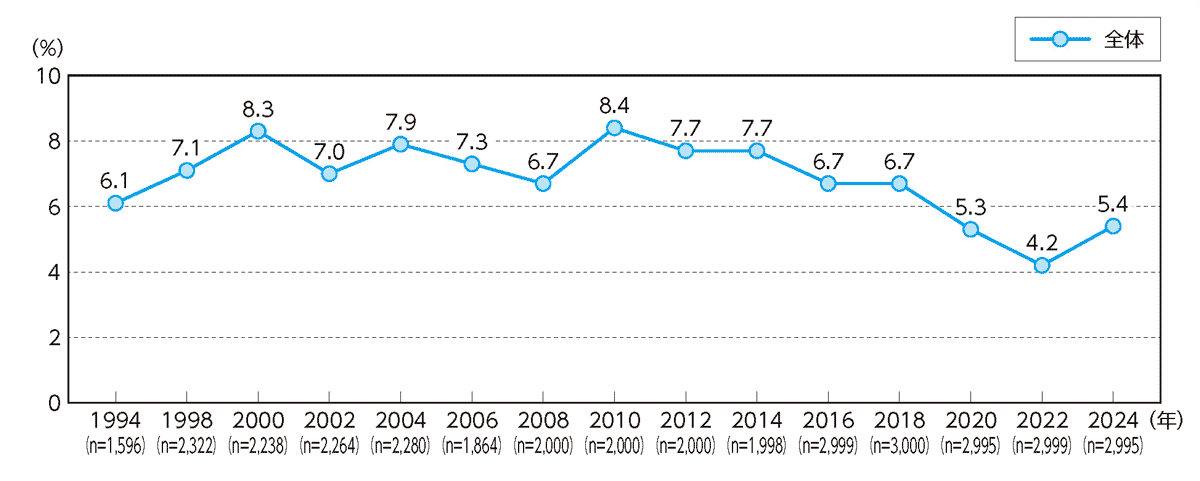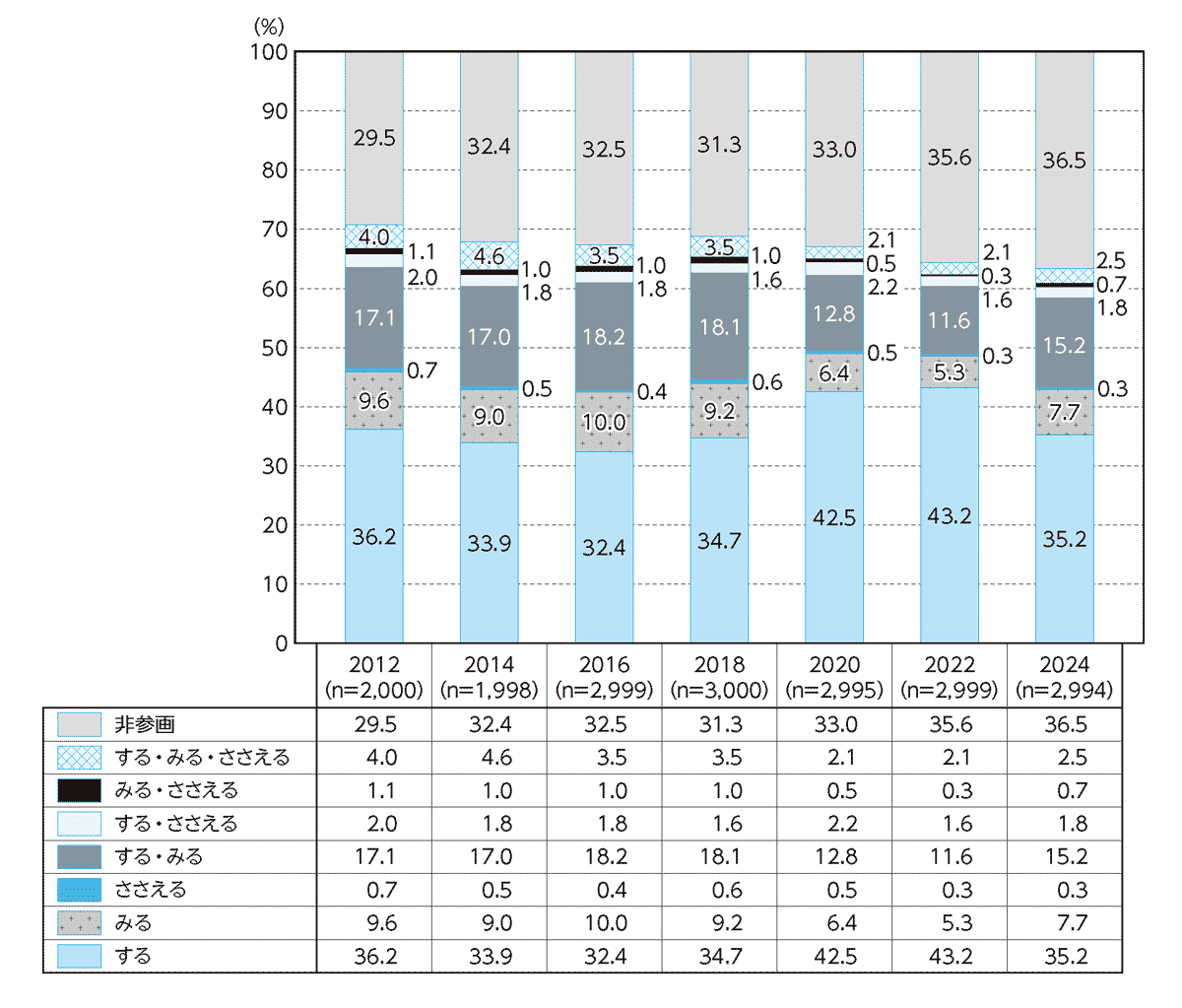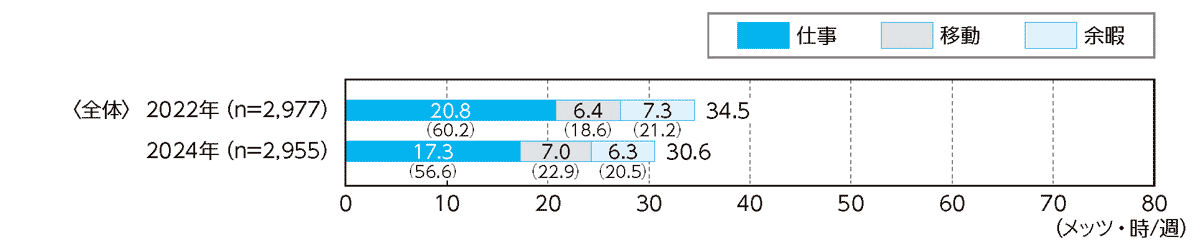【主な調査結果 詳細】
「する」スポーツ
■運動・スポーツ実施率の年次推移
年1回以上の運動・スポーツ実施率をみると、1992年調査では50.9%と半数をわずかに超える程度であったが、2000年には70.7%に上昇した。その後、2006年までは60~70%台の間を行き来し、2008年以降は70%台での横ばい状態が続いていた。2024年調査では69.8%であり、前回の2022年調査から3.1ポイント減少して2006年以来の6割台となった。
図表1. 運動・スポーツ実施率の年次推移
注1) 2014年までは20歳以上、2016年以降は18歳以上を調査対象としている。
注2) アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、運動強度「ややきつい」以上の実施者
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
■運動・スポーツ実施レベルの年次推移
運動・スポーツ実施レベルは、「実施頻度」「実施時間」「運動強度」をもとに、運動・スポーツ実施状況を量的・質的観点から捉えるSSF独自の指標である。
図表2. 運動・スポーツ実施レベルの設定
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
運動・スポーツ実施レベルの年次推移をみると、「レベル4」(アクティブ・スポーツ人口)は、1994年調査の7. 6%から漸次増加し、2012年では20. 0%に達した。2018年は20.7%、2020年の22. 1%で過去最高を示したが、2024年は18. 3%であった。運動強度・時間に関係なく、週2回以上運動・スポーツを行う「レベル2」は9.4%と、1994年調査以降6~10%の間を推移しており、コロナ禍前の2018年9.5%から横ばいである。過去1年間にまったく運動・スポーツを実施しなかった「レベル0」は、1994年は50. 1%と全体の半数を占めていたが、2022年は4分の1程度まで減少した。しかし2024年は30. 2%に増え2006年以来の3割超えとなった。
図表3. 運動・スポーツ実施レベルの年次推移(全体)
注) 2014年までは20歳以上、2016年以降は18歳以上を調査対象としている。
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
「みる」スポーツ
■直接スポーツ観戦率
過去1年間にスタジアムや体育館等で直接スポーツを観戦した者の割合の年次推移を示した。2024年は26. 2%であり、コロナ禍前の水準には戻り切っていないが、2022年19. 3%から6. 9ポイント増加した。
図表4. 直接スポーツ観戦率の年次推移
注)2014年までは20歳以上、2016年以降は18歳以上を調査対象としている。
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
■インターネット観戦率
2024年調査のインターネットスポーツ観戦率は全体の24. 2%で、コロナ禍前の2018年11.5%から12.7ポイント、2022年21.6%からは2.6ポイント増加した。
図表5. インターネットによるスポーツ観戦率の年次推移
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
「ささえる」スポーツ
2024年調査におけるスポーツボランティア実施率は5. 4%で、2022年の4. 2%から1. 2ポイント増加した。コロナ禍前の2018年は6.7%であった。
図表6. スポーツボランティア実施率の年次推移
注)2014年までは20歳以上、2016年以降は18歳以上を調査対象としている。
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
「する・みる・ささえる」スポーツ
「する」「みる」「ささえる」の各スポーツ参画を組み合わせた構成比を示した。前回の2022年と比較すると、「する・みる・ささえる」スポーツ参画は2.5%で0.4ポイント増加とほぼ横ばいであった。いずれにも関わらない非参画は36.5%と0.9ポイントの増加にとどまるが、コロナ禍前の2018年からは5.2ポイント増加している。「する」は35.2%で8.0ポイント減少、「みる」は7.7%で2.4ポイント増加、「ささえる」は0.3%で前回と変わらなかった。
図表7. 「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画の構成比の推移
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024
日常生活における身体活動量
本調査では、国際比較が可能である質問票として世界保健機関(WHO)が開発し、信頼性・妥当性が確認された「世界標準化身体活動質問票(GPAQ)」の質問項目を2020年から採用している。
GPAQでは「仕事」「移動」「余暇」「座位」の4領域に回答し、運動・スポーツを含めた日常生活における身体活動量を把握する。身体活動の強度は安静時を1メッツ※とし、2024年の全体の総身体活動量は30.6メッツ・時/週であり、2022年から約4メッツ減少していた。身体活動量を「仕事」「移動」「余暇」の領域ごとにみると、構成比の内訳は仕事56.6%、移動22.9%、余暇20.5%で、2022年より仕事の割合が3.6ポイント減少し、移動の割合が4.3ポイント増加した。
※メッツ:「安静時を1としたときに、何倍のエネルギーを消費するか」を示す活動強度の単位。歩行は3メッツ、速歩は4.5メッツ、ランニングは10メッツ。週に3時間のランニングを行った場合、10メッツ×3時間=週30メッツ・時となる。
図表8. 身体活動量および各領域の構成比の年次推移(全体)
注)仕事・移動・余暇の身体活動量の下に記載した括弧内の数値は、総身体活動量に占める各領域の割合を示す。
資料:笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2024