2020.12.08
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2020.12.08
1964年の東京オリンピックは10月24日に閉幕した。その2カ月後に「東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典」という書籍が講談社から刊行されている。石川達三、石原慎太郎、井上靖、大江健三郎、小林秀雄、武田泰淳、永井龍男、松本清張、三島由紀夫、水上勉、安岡章太郎など、当時の錚々たる文学者40人がオリンピックを観戦し、それを活字で表現したノンフィクション集である。純文学作家も、推理作家も、評論家も、みなそれぞれの視点で世紀のスポーツの祭典を評価し論じている。一流の文学者にとってあのオリンピックのインパクトが、いかに強烈だったかが伝わってくる。いや、一流の文学者だからこそ、あの大会の質感を迫力ある表現で読者に伝えることができたのだろう。
二度目の東京オリンピックとパラリンピックを前にして、スポーツと文学の関係を今一度考えてみたい。
スポーツ・フィクション
多少荒っぽい言い方をすれば、文学はフィクションとノンフィクションに分けることができ、フィクションはおもに小説を指す。その小説は、芥川賞と直木賞という2つの大きな賞があるからか、純文学と大衆文学に分けられ語られることが多い。その分類についての議論はさておき、まずは純文学としてのスポーツ小説を一遍、その一部を紹介しよう。

三島由紀夫『剣』講談社(三島由紀夫短編全集6). 1971
三島由紀夫『剣』(1963)はスポーツを扱った数少ない純文学である。自身も剣道の有段者であった三島の独特の美学「男のエロスと死」がまさに美しく表現されている。
・ 三島由紀夫『剣』より抜粋
「剣は居丈高に、彼の頭上に高く斜めに懸つてゐる。それを支へてゐる彼の力は軽やかで、丁度剣は、夕月が空に斜めに懸つてゐるやうな具合だ。左足を前に、右足を後に、彼はひねつた体で、じつと敵に対してゐる。その黑胴は、ぢりぢりと相手に応じて向きを変へるにつれて、沈静な光沢を移し、二葉竜胆の金の紋は、左右へさしのべた鋭い黄金の葉を煌めかす」
(「三島由紀夫『剣』講談社・三島由紀夫短編全集6. 1971」より引用)
これは「剣道」を描いた1963年の小説である。じっくり味わうように読むと、一幅の絵のような情景が浮かんでくるはずだ。
剣道は武道だがスポーツである。しかしここでは、まるで江戸時代の月明かりの夜、真剣で戦う剣豪同士の殺気あふれる姿を見ているような錯覚に襲われる。
次は大衆文学としてのスポーツ小説である。
三浦しをん『風が強く吹いている』(2006)は、漫画化、ラジオドラマ化、舞台化、実写映画化、そしてテレビアニメ化された作品だ。司法試験に合格した秀才、ヘビースモーカー、運動経験のない外国人など、一人の天才ランナーを除きスポーツに縁のない一風変わった学生たちが、格安学生寮で共同生活しながら、箱根駅伝に出場するまでのプロセスが描かれる。
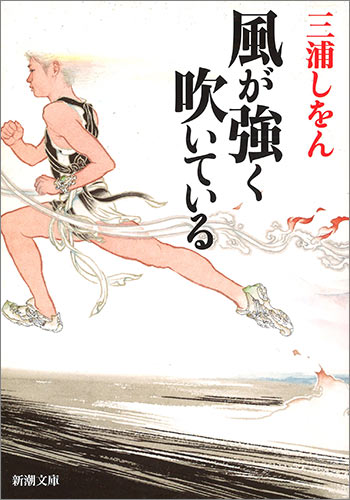
三浦しをん『風が強く吹いている』新潮社(新潮文庫). 2006
・三浦しをん『風が強く吹いている』より抜粋
「ああ───。走(かける)は立ちすくむ。止めることはできない。走るなと言うことはできない。走りたいと願い、走ると決意した魂を、とどめられるものなどだれもいない。
(中略)
俺はたぶん、走ることを死ぬまで求めつづけるのだろう。
たとえばいつか、肉体は走れなくなったとしても、魂は最後の一呼吸まで、走りをやめはしない。走りこそが走(かける)に、すべてをもたらすからだ。この地上に存在する大切なもの───喜びも苦しみも楽しさも嫉妬も尊敬も怒りも、そして希望も。すべてを、走(かける) は走りを通して手に入れる」
(「三浦しをん『風が強く吹いている』新潮社・新潮文庫. 2006」より引用)
主人公の名は、「走」と書いて「かける」と読む。「走る」という動詞と混同しないように読みたい。こちらは純文学とは異なり、表現の美を享受するという読み方ではなく、エンターテインメントとしてストーリーを追いながら読むのが基本だ。そのため、一部分だけでこの作品の魅力を知ることはできない。ただ、このパートを読むだけで、いくらかはこの作品のもつ勢いを感じることはできるだろう。
フィクションである小説では(時代小説を除いて)、通常、主人公をはじめとする登場人物は架空の存在である。しかし、そこに登場するスポーツはフィクションではない。彼らが小説の中で行うスポーツは、野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、ラグビー、陸上競技など、現実に行われているスポーツなのである。フィクションとはいえ、架空のスポーツが登場することは、まずあり得ない。そして、スポーツは小説の中であっても、現実と同じルールで行われる。その部分は、「フィクション中のノンフィクション」なのだ。
スポーツ小説に登場するスポーツはリアルだ。現実のスポーツとまったく同じルール、規則のもとで行われている。たとえ小説の中とはいえ、ラグビーでボールを前に投げてはいけない。トライは5点でコンバージョンゴールによって2点が追加される。マラソンはきっちり42.195kmを走り、フィニッシュするまで誰も選手に触れてはならない。
作家が小説を書くときに力を入れるのは、フィクションでありながらいかにリアルな表現をするかである。作品の舞台に選んだ場所が沖縄の島であれば、その島の地理や気候、食文化、暮らす人々の気質などをこと細かに描写する。鉄道殺人事件を描く場合は、何という路線のどのような列車が舞台となり、どこの駅で事件が起こる、など詳細にわたって実際の鉄道が描かれる。もし作家が間違いを描いた場合は、沖縄や鉄道に詳しい読者からのクレームに悩まされることになるだろう。架空の話であっても、リアルな部分はリアルに描く。そこには小説中の最も重要なフィクション部分を「まるで真実のような嘘」にするための効果がある。「フィクション中のノンフィクション」は、正確に記す必要があるのだ。
スポーツ・ノンフィクション
ノンフィクションを見ていこう。ノンフィクションの概念は幅広い。それは雑誌記事から映像までさまざまなメディアにおいて表現され、史実にもとづいている内容であるのが原則だが、フィクション以外の作品を指すのが一般的である。

山際淳司『江夏の21球』を所収するKADOKAWA『スローカーブを、もう一球』. 1985
ここで紹介する山際淳司『江夏の21球』は「Sports Graphic Number」創刊号(1980.4)に掲載され、その後、角川書店から書籍として発行された。この1作品で山際はノンフィクション作家として広く認められるようになった。
・山際淳司『江夏の21球』より抜粋
1979年11月4日、日本シリーズ第7戦・近鉄バファローズvs広島カープ、9回裏1アウト満塁、3対4で広島リード。
広島カープのピッチャー江夏はスクイズを警戒していた。
「江夏は、いつものように投球動作に入った。江夏のピッチング・フォームには1つだけ、クセがある。それがこの場の結果を左右するとは、江夏自身も思ってはいない。
<おれは投球モーションに入って振りあげるときに、一塁側に首を振り、それから腕を振りおろす直前にバッターを見るクセがついている。(中略)石渡を見たとき、バットがスッと動いた。来た! そういう感じ。時間にすれば百分の一秒のことかもしれん。 (中略) 握りかえられない。カーブの握りのまま外した>
あそこからスクイズを外してくるなんて、しかも変化球で外してくるなんて……ありえない」
(「山際淳司『江夏の21球』KADOKAWA・角川文庫『スローカーブを、もう一球』所収. 1985」より引用)
9回の裏、江夏が21球で相手チームを仕留めるシーンを描いているのだが、著者は、江夏本人やバッター、関係者などをインタビューするとともに、1球1球を分析し、江夏とバッターの心の動きと、それが実際の動作にどのように影響するかを克明に記している。とくにスクイズを外す19球目の描写(上記)は細かく、圧巻だ。
フィクションとノンフィクション、とりわけオリンピックにおいて
スポーツには非日常と非現実が内在している。スポーツ文学におけるノンフィクションであっても、多くの場合、主人公は実在の人物でありながら非現実的な速さ、距離、強さ、美しさを実現するトップアスリートである。何も脚色せずともすでに非日常的なのだ。したがって、作家がそれを詳細に描くだけで、十分にインパクトのあるノンフィクションになる。それはオリンピックにおいて顕著だ。
オリンピックが終わるとスポーツ誌を中心に、ルポルタージュ=ノンフィクションが掲載される。実際の出来事を切り取り、そこに強弱をつけたり演出を加えたりしながら描くことで、ノンフィクションは現実のことでありながら、まさに驚異的なインパクトを読者に与える。モチーフであるオリンピックで繰り広げられるパフォーマンスやハプニングが、あまりにもドラマティックであるからだ。
ノンフィクションは「よい素材」と「すばらしい構成・表現」で読み応えのあるものになる。スポーツ・ノンフィクションにおける「よい素材」とは、ただ金メダリストのような世界のトップを紹介すればよいというものではない。その人が途中で大きな挫折をしていたり、何らかの悲劇を乗り越えて優勝するなど、大きな変化があるほうが読者の感動を誘う。
たとえば、1998長野冬季オリンピックのスキージャンプ団体の金メダルは、4年前のリレハンメル大会で、金メダル間違いないという状況で失敗し銀メダルに終わっていたことで、感動がより際立った。
試合中に肉離れのケガを負い、それでも勝った柔道の山下泰裕(1984ロサンゼルス大会)や、残り数秒で大逆転したレスリング4連覇の伊調馨(2016リオ大会)も同様だ。苦労してつかんだ勝利や、起死回生の大逆転などは、すでに感動のストーリーができ上がっているのと同じなのだ。それが非日常的であればあるほど、凄みが増す。
2014年ソチ冬季大会フィギュアスケート女子シングルの浅田真央を思い出してほしい。世界が認める天才スケーターがショートプログラムで16位になるなんて誰が想像しただろう。その浅田がフリーで完璧な演技を披露し世界に感動の嵐を巻き起こしたあの4分間は、まるで作られたドラマのようだった。そんなフィクションのような現実を創り出してしまうのが、オリンピックという非現実的な現実なのだ。
その意味で、オリンピックで競われるスポーツは、フィクションでは扱いづらいテーマである。究極のスポーツの集合体の中では想定外の事件が起こりうる。行われるスポーツそれ自体が非日常的であるだけでなく、展開される出来事が極めてドラマティックであるため、それを超えるフィクションを創造するためには涙ぐましい努力が必要になるだろう。かくして、スポーツ文学においては、フィクションとノンフィクションを分ける境界線は、極めて薄くなる。
フィクションが、トップスポーツの場に出現する非現実的なインパクトを超えるためには、三島由紀夫の『剣』のように、スポーツであるはずの大学運動部の剣道を、殺気みなぎる真剣での斬り合いを彷彿とさせる場面に変えてしまうことや、三浦しをんの『風が強く吹いている』のように、運動経験のない外国人やヘビースモーカーがいきなり箱根駅伝を走ってしまうような、現実離れした状況を作り出すほかはない。しかしそれができるのは、三島や三浦のような力量のある作家に限られるだろう。
それにしてもオリンピックは強烈だ。ドラマが凄すぎて、なかなかフィクションが追いつけない。それはきっと、オリンピックに棲んでいるといわれる魔物のせいにちがいない。
関連記事
 大野 益弘
日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。
大野 益弘
日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。