2020.06.23
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2020.06.23
あれは2012年夏季オリンピックの開催都市が決まる前、確か2005年の春だったと記憶している。
マドリードにパリ、ニューヨーク、モスクワ、そしてロンドン。世界の名だたる都市が立候補、まるで世界大都市戦争のようで、どこが選ばれても不思議ではない状況にあった。この年国際オリンピック委員会(IOC)副会長に就任する猪谷千春さんに、不躾にも「どこが有利か」と聞いてみた。
「ロンドンがいい印象を持たれている」
猪谷さんは招致委員会会長を務めるセバスチャン・コー氏の活動ぶりをあげて、IOC委員の雰囲気を話してくれた。そして、話のついでにこんなことを言った。
「イギリスはバーミンガムとマンチェスターが2度、立候補して負けているでしょう。背水の陣で立候補したロンドンにIOC委員の同情票が集まっているんです。それとね、IOCはロンドンに借りがある。それを、とくに古いIOC委員たちは忘れていません」
ロンドンに借り? 前段の「同情」はよくわかったが、後の「借り」とは何なのか? それが気にかかった。

1948年ロンドン大会開会式の聖火入場
「戦後初、1948年に開催されたロンドン大会のことです。ヨーロッパやアジアで長く続いた戦争の影響で1940年、1944年とオリンピックが中止され、この1948年第14回大会が無事に開催されなければオリンピックの長い歴史はここでおしまいになるかもしれない。まして戦後の混乱した時代、ロンドンだって疲弊していたでしょう。それでも開催を引き受け、見事に大会を成功させた人たちへの感謝をIOCは忘れていないんです」
思わずうなった。50年以上、60年ちかい歳月を超えて、戦後初の大会開催への感謝がIOCに伝えられている。1948年第14回ロンドン大会の持つ意義、重さである。
ちなみに、2012年第30回大会は当時のトニー・ブレア首相の熱のこもった招致スピーチも手伝ってロンドン開催に決定。あの「近年、最も成功した」と称賛される大会につながったことはよく知られている。

1928年アムステルダム大会の金メダリスト、デヴィッド・バーリー
時計の針を1945年に戻そう。第2次世界大戦でアドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツが5月に降伏、それから2カ月後のことである。
英国のIOC委員で英国オリンピック委員会(BOC)会長のデヴィッド・バーリー(後の第6代エクセター侯爵)はIOC会長、ジークフリード・エドストロームをストックホルムの自宅に訪ねてこう告げた。
「ロンドンで次のオリンピックを開催しようと思っている」
当時、ヨーロッパの都市は戦争の影響で疲弊していた。英国、ロンドンも例外ではなかった。しかし、バーリーは動いた。「世界中が疲弊しているからこそ、近代スポーツ発祥の地として英国が先頭に立たねば……」との思いからだったとされる。ノブレス・オブリージュ※、長くオリンピックムーブメントの先頭に立ってきた者としての危機意識に裏打ちされた犠牲的な精神だったろうか。
※社会的地位の保持には義務がともなうこと。
彼はオリンピアンであった。1928年第12回アムステルダム大会陸上競技400mハードル金メダリストとして輝かしい競技歴が歴史に刻まれている。1924年パリ大会にも、あの映画『炎のランナー』の主役のひとり、ハロルド・エイブラハムと同じケンブリッジ大学の一員として出場していた。
後に国際アマチュア陸上競技連盟(現・国際陸上競技連盟=IAAF)会長、IOC副会長を務め、会長となるエイベリー・ブランデージの対抗馬として会長候補に担がれたこともある。オリンピックへの思いは誰よりも強かったということができよう。
8月、IOCの理事たちはロンドンに集い1948年大会をどうするか、話し合った。すでにIOC本部を置くスイスのローザンヌとアメリカの4都市(ボルチモア、ロサンゼルス、ミネアポリス、フィラデルフィア)が開催に名乗りを上げていた。理事たちはそこで、IOC委員の郵便投票による決定を選択した。戦後処理の混乱が続き、IOC委員全員が集まる場所、費用に支障がある。恒例のプレゼンテーションを取りやめたのは致し方のない話ではあった。
IOC委員たちは開催地にロンドンを選んだ。正式な決定は翌1946年である。バーリーは、スポーツ愛好家で知られる貴族や上流階級の人たちを集めた。クラレンス・ブルース=アバーディア男爵(のちにIOC委員)やノエル・カーティス=ベネット男爵(のちBOC会長)、そしてあのハロルド・エイブラハムなども加わった。
イギリスに余裕があったわけではない。ほかの国々と同じように戦争に疲れ、国内には憤懣が渦巻いていた。食糧事情の悪さに改善は見られず、戦時中同様に配給が続く生活。町の中心部には空襲の跡が残り、住宅は全国的に不足していた。「まずは復旧・復興を優先させるべきではないのか」と、50有余年後の2020年東京大会でも東日本大震災からの復興を抱え、聞こえてきた反応と同じだ。
植民地として運営してきたインド、パキスタンが独立に動き、セイロン(現・スリランカ)やビルマ連邦(現・ミャンマー)がそれに続こうとしていた時代。「大英帝国」は海外との関係でも混乱のただなかにあった。

フィリップ・ノエル=ベーカー氏
オリンピック開催は決まっても財政の困窮状態はいかんともし難い。デヴィッド・バーリーたちは政府を頼った。時の首相、クレメント・アトリーはスポーツ好きで知られる。アトリー首相は早速、支援を表明し、閣僚のひとりをオリンピック担当大臣に任命。担当大臣を中心に事が運ぶよう体制を整えた。
フィリップ・ノエル=ベーカー(後に男爵)。ケンブリッジ大学出身の政治家であり、戦前、ウッドロウ・ウィルソン米大統領を支えて1920年の国際連盟創設に尽力。同時に同じ年のアントワープ大会陸上競技1500mで銀メダルを獲得したオリンピアンでもある。戦後すぐの混乱期、アトリー内閣に迎えられて国務相兼任として1945年10月25日に誕生した国際連合の英国代表を務めてもいた。
スポーツを、オリンピックをよく知る政治家の登場は、大会準備を一気に加速させた。
英国のスポーツライター、デイビッド・ゴールドブラッドの大著『オリンピック全史』によれば、ノエル=ベーカーは内閣の意思統一に向けてこう進言したという。
「オリンピックがここロンドンで開かれる以上、その成否には国家の名誉がかかる」
フィリップ・ノエル=ベーカー男爵の登場によって大会開催は国家事業となっていく。イギリス国鉄は選手団と関係者の運賃を半額とし、ロンドン交通局は無料にした。軍需省はワゴン車やバスを提供し、輸送業務を担当した。食糧省は鉱山や海運に従事する肉体労働者と同じカテゴリーの食糧を選手に配給すると決めた。
陸、海軍が施設と人材、物資を提供して支援に乗り出し、陸、空軍所有施設の選手村使用も決まった。女子の選手村は大学の寮である。家具は介護施設や自動疎開施設などの備品が提供され、競技会場は既存の施設を使用することになった。オリンピックスタジアムにはサッカーの聖地、ウェンブリー・スタジアムをわずか17日間で改装、各国・地域の選手団を迎える準備を整えた。地下鉄の駅からスタジアムに至る歩道整備には英国内に収容されていたドイツ軍捕虜が従事した。
すべてにノエル=ベーカーが関わったわけではない。しかし、道筋をつけたことは間違いない。ノエル=ベーカーはその後、「核兵器廃絶・軍縮運動」の先頭に立ち、1959年ノーベル平和賞を受賞。史上ただ一人、オリンピックとノーベル賞のメダルを受賞した人物として広く尊敬の対象となっている。
徹底した節約と緊縮財政。それでも大会主催者たちは奮闘した。
こうした状況を冷めた目で見ていた人々もいた。その代表がマスコミである。ロンドン・タイムズ紙やイブニング・スタンダード紙などは「いまのイギリスに大会運営ができるのか」と懐疑的な論調を掲げ、「国民の思い入れを平均すると、無関心から嫌いの範疇に入る」と書いた。
しかし、参加を決めていた各国関係者の思いはマスコミの論調とは異なっていた。開催に腐心する姿に、「われわれもイギリスを手伝おう」との動きが広がったのである。
スウェーデンは競技会場を改装するための木材を送ってきた。馬術競技に使う馬が不足していると聞いて提供を申し出たのはアルゼンチン。そして英連邦の一員であるカナダやオーストラリアは選手村で各国・地域からの代表選手に提供される食料を援助した。どこの国も苦しい時期、開催を引き受けたイギリスに対するせめてもの「御礼」であった。
こうしたことから12年ぶりに開かれた大会は「友情のオリンピック」と称される。
大会には過去最多59カ国・地域から4064人の選手が参加、ウェンブリー・スタジアムでの開会式に臨んだ。英国から独立したインドとパキスタン、セイロンにビルマ連邦、さらには旧植民地だった英領ギアナ(現・ガイアナ)やジャマイカ、シンガポールにトリニダード・トバゴが初参加。南米からベネズエラとプエルトリコ、アジアからはイラン、イラク、レバノン、シリア、そして韓国とフィリピンも初めて行進の列に加わった。
「スポーツを愛する世界中の男女は、その愛の力によって、距離も言葉の違いをも乗り越えた友情の絆で結ばれるでしょう。愛はすべての国境を越えるのです」
アトリー首相は各国・地域からの選手たちを迎えるにあたり、ラジオでそう演説した。前記の『オリンピック全史』は、「これこそ正真正銘のオリンピック思想である」と記し、「フィリップ・ノエル=ベーカーが起草した文章と考えて間違いない」と断じている。アトリー首相の談話からロンドン大会が「友情の」という冠を背負うきっかけになったと考えられる。
ともあれ、消滅の危機にさえあったオリンピックは見事に再起。オリンピックムーブメントは復活した。その根底にはスポーツとオリンピックを愛し、可能性を信じ続けたイギリスの「ジェントル※」と称された階層の人々の熱い思いがあったと思う。古き、良きスポーツマン精神が生きていた時代である。
※穏やかであるさま、転じて紳士。
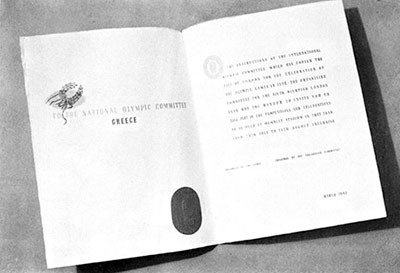
1948年ロンドン大会組織委員会が各国・地域のオリンピック委員会に向けて発行した招待状(写真はギリシャ宛)
大会はまた「アドルフ・ヒトラーの大会で始まったから」と忌避されかけた聖火リレーの存続を決定。今日の「大会の華」に結実させていく。
IOCは5つの輪を象徴するオリンピック・シンボルの管理を強化。「より速く、より強く、より高く」というオリンピック・モットーの独占所有も"宣言"している。
そうしたなかでテレビ中継を担当した英国放送協会(BBC)は中継カメラを観客席に持ち込み、「座席占有料」の名のもとで3000ドルを支払った。今日、IOC財政を支える放送権料の始まりである。
いまに続くオリンピック大会の基本構造はまさに、1948年ロンドン大会から立ち上がったといってもいい。だからこそ、IOCは60年ちかく経っても、「ロンドンへの感謝」を申し伝えているのかもしれない。
残念なことに、1948年の輪のなかにドイツと日本の姿はない。スポーツを統括する組織がまだできていなかったというのは表向きの理由。いうまでもなく第2次世界大戦を引き起こし、世界を混乱させたとされる両国への責任追及から大会には招かれなかった。ちょうど日本では競泳の古橋廣之進の絶頂期が始まる。もし、古橋が参加していたなら……との話は今なおオリンピック関係者のなかでささやかれる。それを逆ばねに、日本スポーツ界が育っていったことも事実である。
戦後初の1948年ロンドン大会は、その後のオリンピックのあり様を定めた極めて重要な大会として記憶したい。
 佐野 慎輔
尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員
佐野 慎輔
尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員