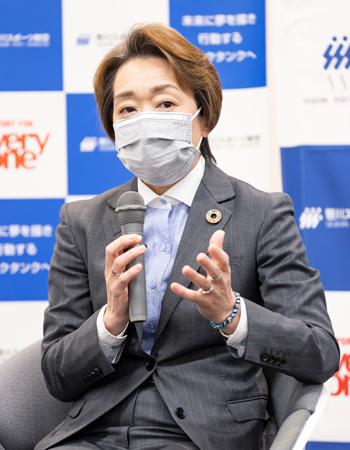スポーツ基本法がもたらした影響
渡邉 2011年にスポーツ基本法ができておよそ10年が経過しました。制定当時の議論と、その後のスポーツ界への影響についてどうお考えでしょうか。
橋本 スポーツには「する」「みる」「ささえる」人がいて、今は「あつまる」という点にもスポーツの価値があるといわれていますが、まずはスポーツとは何か、どこからどこまでがスポーツなのか、運動とは何が違うのか、という根本的な議論を始めました。法制化に携わる国会議員にそういった基本的なことを理解していただくことが難しかった、というのが最初に思い出されます。
オリンピック・パラリンピックという最高レベルのスポーツがある中で、私が現役選手だったころは、トップスポーツでも趣味の延長としかみてもらえない時代でした。そういった過去の認識から、教育や芸術や文化、あるいは医学や科学の観点からスポーツをみることによって大きな価値が生まれ、社会に貢献することができる大きな産業である、という新しい認識に変えていただきながら法律をつくり上げていった過程、そして国の責務をどこにもっていくかという議論が大きなポイントだったと思います。
室伏 私は初代・鈴木大地長官の後を継いで2020年 10月にスポーツ庁長官に就任しました。国の法律ができたことは本当に大きな前進だったと思います。その流れで東京2020大会の招致もありました。障害者スポーツに関する事業が厚生労働省から文部科学省に移管、スポーツ庁が設置され、東京2020大会の開催はひとつの集大成になったと思います。その間にプロスポーツリーグも増え、地域密着型で選手が活躍し、地元住民も参画して地域が活性化していくという流れにもなったと思います。法律が制定されたことにより、この10年は行政も法律をもとに指針を打ち出し、多くの方々の後押しもいただきながら、大変よい形で進んできていると思っています。
渡邉 スポーツ基本法ではスポーツへの国民の参加促進に関して定められていますが、スポーツへの参加が健康に寄与するという点についてどのようにお考えでしょうか。
室伏 スポーツ庁は第3期スポーツ基本計画で、週1回のスポーツ実施率の目標を65%から70%に引き上げました。スポーツが健康によいとわかっていてもなかなか行動に移せない方もいらっしゃる中で、スポーツ庁では Sport in Lifeプロジェクトなどを通じて、国民の皆様に日常生活の中でスポーツに親しんでもらう取り組みを推進しています。
一方で、今後はただ運動をするというだけでなく、具体的に個々に合った運動の仕方や、どのような運動をすれば神経系や循環器系、内分泌系やメンタルなどに効果があるのかというところまでサイエンスベースで取り組んでいく必要があると考えています。スポーツはメタボリックシンドローム対策だけでなく、メンタルを含めてもっと広範囲に貢献できるので、その効果を国民の皆様に届けることができるよう専門家の皆様と一緒に取り組んでいきたいと考えています。
北出 私は産婦人科医ですが、医学の立場からみてもスポーツは絶対に取り入れるべきだと思っています。スポーツがメタボリックシンドロームや糖尿病、高血圧症といった疾患の治療に役立つという意味もありますが、疾患自体を予防する予防医療という視点が非常に重要です。
医学の世界では運動が健康に結びつくさまざまなエビデンスが発表されています。たとえば、運動している人は認知症発症率が有意に低い、運動がうつ病の発症を抑えるなどというデータです。産婦人科では近年、お産後に発症するうつ病が問題になっていますが、運動が産後うつ病の予防に効果的であることもわかってきました。
コロナ禍の閉塞感で若い女性の自殺が増えるなど、世代によらずメンタルにダメージを受けやすくなっています。スポーツと医学はとても相性がいいので、もう少し医学界とスポーツ界が連携し、スポーツの効果に関するエビデンスを社会に還元していくことが重要だと思っています。
渡邉 スポーツによる健康づくりについては厚生労働省やスポーツ庁もさまざまな政策を打ち出しています。そうした中でさらにスポーツ実施率を高めるためには、どのような取り組みが考えられるでしょうか。
北出 まず、スポーツの敷居を下げることが重要かと思います。スポーツと聞くと本格的なものを想像し拒否反応を示す方もいると思います。数年前にイギリスでどんな女性でも運動ができるようにしようというキャンペーン(「This Girl Can」)があり、あえて肥満気味の中年女性が一生懸命運動している写真をポスターに使いました。
これはスポーツのハードルを下げた一例ですが、性別や世代、職業により、スポーツのどの部分に魅力を感じるかは異なります。競技や順位づけの有無に関しても好みは人それぞれで、ひとりで運動するのが好きな方や大勢で楽しみたい方もいるはずです。これらの多様性に応じた施設・イベントなどがあればさらによいと思います。
橋本 私は国がナショナルトレーニングセンターなどを設置する過程に携わり、スポーツは食や科学、あるいは観光など、さまざまな分野を結びつける力があると感じました。その魅力をまずはスポーツ界がもっと結束をして発信し、国がその発信力を高めるためのサポートをしていく必要があると思います。その連携がまだ足りないのかなと感じています。
昨今のトップアスリートの活躍は医学と科学の力によるところが大きいと思います。今までは経験に頼っていたものを、医学と科学によって理解し、正否をしっかり判断して、競技力の向上につなげることができるようになりました。その経験を今度は人びとの健康、身心はもちろん、社会的な健康に役立てていきたい。たくさんのエビデンスをより多くの方々のお力を融合させて発信するところに力を注いでいく必要があると思っています。
またスポーツを普及させる、人びとの生活の一部にスポーツの素晴らしさを活かしていく、役立ててもらうと考えたときに、これはすべての省庁が一緒になってこの問題に取り組んでいかない限り、強く発信していくことはできないと考えています。たとえばサイクリングロードやランニングロードは国土交通省の管轄になりますが、スポーツ庁の視点が入ればよりスポーツにも適した道路ができるのではないでしょうか。農林水産省の視点も加われば、心を癒やしてくれるような田園風景を楽しめる道路ができるかもしれません。こうした視点が分断されてしまうと、結果として使い勝手の悪いスポーツ環境になってしまいます。それぞれのもつ力を結集することが必要だと強く感じています。
室伏 橋本先生のおっしゃるとおりで、文部科学省だけでスポーツ政策は完結できないと思いますし、他省庁との連携が大事との考えからスポーツ推進会議を開催しています。厚生労働省、農林水産省、国土交通省、外務省など各省庁とディスカッションをしていますが、スポーツへの関心は皆様本当に高いです。東京2020大会のレガシーでもありますが、この関心の高さを活かして省庁の縦割りをいい意味で破る方向にもっていき、ご指導いただきながら進めていくことが、国民のスポーツ実施率のさらなる向上に結びつくと考えています。
東京2020大会がもたらしたレガシー
渡邉 東京2020大会が終わって1年半しか経っていませんが、大会がどのようなレガシーを残し、そのレガシーをどのように継承・発展させていくべきと感じているでしょうか。
室伏 東京2020大会を通じて確認されたスポーツ・レガシーの継承・発展に向けて、今後5年間の基本的な指針として策定された第3期スポーツ基本計画に基づき、「スポーツを通じた共生社会の実現や多様な主体によるスポーツ参画の促進」「スポーツによるまちづくり・経済発展の推進」「スポーツを通じた国際交流の推進」などの取り組みを着実に進めることが重要だと考えています。
スポーツ庁としては、スポーツの力で社会が活性化し、その社会がスポーツをささえるような好循環が構築される「スポーツ立国の実現」に向けて、必要な取り組みを進めていきます。
橋本 オリンピック・パラリンピックは世界最高峰のスポーツの祭典といわれています。その祭典を迎える国や都市は、世界の見本にならなければならないとの意識をもって、東京2020大会を迎えるまでの約8年を過ごしてきました。
「多様性と調和」の観点では、パラリンピックから学ぶことは大きかったと思います。障害の有無に関わらず誰もが集える場所を準備して、ユニバーサルデザインの街に一歩近づくことができました。そしてパラリンピックに出場した選手たちの活躍により、体の不自由な人がこれだけのことをできる、ということが広く国民に伝わったのではないでしょうか。いろいろな人たちがいて、そこに人と人とのつながりが生まれてささえ合う。自国開催により、そういったことが社会全体に行き渡っていったことは大きなレガシーのひとつになったと感じています。
世界に向かって重要な技術革新を発信できたこともレガシーのひとつになったのではないでしょうか。聖火台の燃料としてオリンピック史上はじめて水素を使い、全国各地から集めたリサイクル金属でメダルをつくるプロジェクトなど、新たな取り組みとして行えたこともこの大会の大きな価値でした。ただ、残念だったのは無観客であったことです。会場での一体感をその場で感じ、発信することができれば、さらに意義のある大会になったでしょう。
室伏 障害者スポーツ、パラリンピックの成功は、東京 2020大会の大変重要なポイントだと思います。パラリンピックで活躍する選手をみて学んだことは、我々の心にバリアがあり、それが健常者と障害者の間に壁をつくっているのではないか、ということです。身体的なこと以前に「これはできないんじゃないか」とバリアをつくってしまっているのではないでしょうか。パラリンピックをみて、考え方を変えればできるんじゃないかと思った方がたくさんいたとすれば、パラリンピックは大成功だったと思います。無観客ではありましたけど、映像は残っていますので、ぜひ国民の皆様にも何度も見直していただきたいです。しっかりとレガシーを継承して、国民レベルで健康増進やスポーツに親しみ、日常の喜びにつなげていくことが大切だと考えています。
また、障害の有無に関わらず、多様な方が運動できる場を提供することは大切です。昨年8月に障害者スポーツ振興方策に関する検討チームに報告書をまとめていただいて、「障害の有無に関わらずスポーツに親しむ機会を創出すること」と提言していただきました。「障害の有無に関わらず」という点については、個人的には障害者と健常者で施策を分けるべきではないと思っています。分けてしまうと別々の道を歩き始めてしまいます。
すべてがそうではないですが、障害者の受け入れ先がないという話も聞きます。しかし、本当に受け入れ先がないのかといえば、私はそうではないと思っています。たとえば指導体制です。普段は健常者を教えているコーチやトレーナーが本当に障害者の指導はできないのか。私はできると思っています。気をつけるべきことに留意することで可能になるはずです。私も教えたことがありますが、その人に合う指導が大事です。医師から運動制限がかけられているのであれば、事前にできることを把握することで、指導の大きな問題に発展することはなくなるでしょう。健常者、障害者とあまり分けずに取り組んでいくことで多くの問題を解決できるのではと感じています。
来年度には、障害者を指導する場合のガイドラインを策定したいと考えています。障害者のための指導者を増やすのではなく、障害者と健常者のどちらも変わらず指導できるようにするという考え方です。施設についても、障害者スポーツセンターを活用いただきつつ、ほかにも使える場所があるはずです。大事なのは可能性を広げること。こうしたところを推し進めていくのも東京2020大会のレガシーではないかと思っています。
北出 東京2020大会では「多様性と調和」がすごく重要視され、パラアスリートの活躍やLGBTQの選手たちの声も多く届き、その点は非常に大きな変化でした。また、以前に比べて女性の活躍が目立ち、男女ペアの混合ダブルスなどを取り入れた競技もあり、新しい流れを感じました。
一方、女性アスリートの特徴として、引退時期が男性アスリートと比較して早いという点があります。出産後に復帰するタイミングが難しいこともありますが、女性アスリートの三主徴といわれるように、女性ホルモンの影響で女性の方が相対的エネルギー不足に陥りやすい傾向にあります。ジュニア期からその状態にあると、成長期が遅れたり、疲労骨折や無月経が起こりやすくなったりするという問題もあります。こうした中で選手生命をいかに伸ばすかは大きな課題であり、選手や指導者をはじめ地域の産婦人科医にもこれらの問題を周知する必要があると思っています。
ジェンダー問題にはいろいろデリケートな部分があります。以前、女性でも男性ホルモンの値が高い性分化疾患の選手が、テストステロン値を制限する規定の撤回を求めてヨーロッパ人権裁判所に提訴したことがありましたが、彼女たちの精神的ダメージを考えると、これらも早急に解決すべき課題かと思います。
橋本 私が初出場した1984年サラエボ冬季オリンピックは、それほど観客は多くなく、すべての競技が注目されてみてもらえるような時代ではありませんでした。最近は競技施設も改善され、アスリート自身がいろいろな発信をすることもできファンが増えていますが、まだ競技によって観客動員の温度差があるので、より身近に感じてもらえるように発信する必要があると思っています。
今回の東京2020大会は映像を通して本当に多くの方々に競技をみていただき、特にパラリンピックをみた多くの方が「なぜあんなことができるんだ」と感じたのではないでしょうか。その姿に「自分も頑張らないといけない」と刺激を受けた人も多いと思いますが、実際に一歩踏み出し、行動を起こした人はあまりいないように感じています。どうしたら行動に移してもらえるのか、実際にチャレンジすることができるのか、というところが非常に重要です。
室伏 東京2020大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、史上初の1年延期・原則無観客となりました。練習環境も大幅に制約され、選手にとっては、これまでに経験したことのない厳しい環境の中での大会だったと思います。そのような中で、日本代表選手が、精一杯努力し、みずからの限界に挑み懸命にプレーする姿は、多くの国民に勇気や感動を届けてくれました。
また、スケートボードなどの競技において、難度の高いパフォーマンスに挑戦した選手を対戦相手が称賛し合う姿は、勝敗だけではないスポーツがもつ価値を伝えてくれました。さらに、国籍、性別、年齢、障害の有無に関わらず、多様なアスリートが集い、競い合い、互いを認め合う姿は、スポーツを通じた共生社会の価値を実感する契機ともなりました。アスリートには、今後もスポーツに真摯に向き合う姿を通して、スポーツのもつさまざまな価値を社会に発信し、わが国に活力をもたらす役割を担っていただくことを期待しています。
そして、多くの困難を乗り越え、道を切り開いてきたアスリートとしての貴重な知見をぜひ次の世代に伝えていただきたいと思います。
渡邉 残念ながら無観客となってしまった東京2020大会ですが、代わりにボランティアの活躍がメディアに取り上げられました。実際に国内のさまざまなスポーツをボランティア活動がささえています。ボランティア文化の定着や共生社会の実現など、レガシーを継承・発展させていく上で、国民の皆様とどのように連携・協力していく必要があるでしょうか。
橋本 これまで、ボランティアというと「困っている人を助ける」とか「誰かのために」というイメージでしたが、東京2020大会におけるボランティア活動は、ボランティアの皆様がアスリートや大会運営側と一体となり、同じ方向を向いて何かをつくり上げていくという作業だと感じました。
東京2020大会では、約70,000 人(うちパラリンピックは24,514人)の大会ボランティア、約12,000 人の都市ボランティアが参加してくださいました。
コロナ禍で限定的にならざるを得なかった活動もありましたが、さまざまな交流もありました。一方、ボランティアからは役割や待遇について不満の声もありましたし、せっかく参加していただいたのに満足感の得られる活動内容を構築できなかった部分もあります。
しかし、よかった面も悪かった面もレガシーだと感じています。組織委員会は時限的組織でしたが、それぞれの自治体は、これからネットワークを維持、発展させ、常に情報共有できればと思います。今後、参加してみようとする人たちのためにも、成功例や失敗例がみられるようにしておくことも有効だと思います。
室伏 東京2020大会ではボランティアの方々が活躍する場が限定的になってしまったのは残念です。本来であればボランティアはその活動をとおして得たものをご自身の日常に活かしたり、国際交流も含めて新しい仲間を増やしたり、さまざまな価値観の方々と共同で仕事をして得られることがたくさんあると思います。今後も国内では世界水泳や世界陸上、アジア競技大会なども含めて多くの国際大会が開かれます。こうした大会に積極的に携わることは人生の素晴らしい経験になるのではないかと思いますので、ぜひボランティアにも興味をもっていただきたいと思います。
北出 東京2020大会でのボランティアの方々の活躍はまだ記憶に新しいですが、パンデミックに加えて猛暑の中で、世界中からの選手達を直接ささえることができる唯一の市民代表としてさまざまなプレッシャーもあったと思います。しかし彼らはそれをものともせず、ゲストたちをしっかりサポートし、笑顔で応援し、そのおもてなしの精神が素晴らしかったと海外メディアでも取り上げられました。その働きは、不慣れな環境下で戸惑う選手たちにとっても大きな助けとなり、スポーツをささえることの重要性が国民にも伝わったことと思います。また感染症や熱中症対策を踏まえてボランティア活動におけるマニュアルもブラッシュアップされ、今後さまざまな国際大会で幅広く活用されることを期待しています。直前まで開催の是非が問われた大会でしたが、アスリートが全力で競技に挑み、励まし合う姿に感動し、予想をはるかに超えたスポーツの力を感じずにはいられませんでした。トランスジェンダーの選手の出場、パラアスリートの活躍も注目され、多様性を認め合う共生社会の重要性を認識するよい機会になったと思います。
地域スポーツの大きな転換期となる 運動部活動の地域移行
渡邉 運動部活動の地域移行は、子どものスポーツ環境を再編するきっかけとなり、地域スポーツ推進のありかたにも大きな影響を及ぼす、スポーツ界の大きな転換期となるはずです。子どものスポーツ環境を整えながら、地域スポーツをどのように推進していくのかについてご意見をお聞かせください。
室伏 部活動に関しては2022年6月に検討会議の提言を受けて、まずは週末の運動部活動を地域単位で3年間を改革推進期間とし取り組んでいます。国、学校設置者、地域がしっかりと連携してやっていけるかということになります。
地域単位での部活動のサポートにはさまざまな形があります。総合型地域スポーツクラブが関与する、学校の施設を借りて外部の指導者が来る、学校の先生が兼業の申請をしてクラブの指導をする、というケースもあります。これにより子どもたちがより専門的な指導者に教えてもらえる環境に近づくと思います。
また、部活動の地域移行のメリットは専門的な指導を受けられることだけではありません。たとえば女子でサッカーをやりたいと思っても、なかなか女子サッカー部のある学校は少ないのが現状です。じゃあどこでやるのか、地域でやろうという流れです。オリンピック・パラリンピックの競技でも学校単位では経験できないものが多いですが、地域で体験できるようにしていこうとしています。
経験格差は重要なポイントです。豊かな経験をする子どもたちが増えれば、将来のわが国の発展に結びつくような人材の育成につながると思います。障害者スポーツも大いに経験してほしいですし、こうした社会教育の意義は大きいと感じています。
橋本 今、学校現場では教員の方々が大変苦労されています。部活動で子どもを教えることができる専門性のある先生が少ないという問題もあります。これを国としてサポートしていこう、もっと地域で部活動をささえていこうという流れですが、その先に何があるのかをしっかり考えていく必要があると思います。それは、学校が子どもたちだけの場所ではなく、その地域の人びとが集う場所、昔ながらのコミュニティを復活させるような場所にしていくということです。
北出 運動部活動の地域移行では、教員の負担や指導者不足を解決するだけでなく、子どもたちが学校内という閉鎖空間から飛び出して自由に運動ができ、またさまざまな運動の選択肢が与えられ、専門的な指導を受けられるという大きなメリットもあるはずです。
学校の部活動では、指導者や部員と折り合いが悪くなっても簡単に部を辞められず、精神的なストレスを感じる生徒がいることをときどき女性アスリート外来でも耳にしますが、この政策により救われるきっかけになればよいと思いました。子どもたちが学校の垣根なく自由に好きな運動が楽しめれば、スポーツ実施率の向上にもつながりそうですが、行政と地方自治体、民間施設がどのように連携して取り組むかも重要な課題かと思います。
第3期スポーツ基本計画とスポーツの価値
渡邉 国づくりという観点からスポーツの果たす役割を考えたいと思います。今後は健康長寿社会や共生社会の実現がわが国の課題になってくると思われますが、こうした社会をつくりあげるために、スポーツの価値をどのように活用していくべきとお考えでしょうか。
橋本 私自身はスポーツ医学の根底にある考え方がもっと世の中に広がればいいと考えています。スポーツ医学は予防医療なんです。選手の体をいい意味でコントロールし、万全の状態で試合に臨めるようにします。一方でわが国の医療は多くが対症療法となっています。いろいろと難しい問題はありますが、同じお金をかけるのであれば予防医療に力を入れたほうが健康寿命も延び、終末医療にかかるお金もまったく変わってきます。こういったところをスポーツの力で変えていくことができないかと考えています。
人間は社会的地位や経済力があれば健康で幸せかといえば必ずしもそうではありません。人とのつながりをもって、楽しく生きがいをもつことで幸福度は上がっていきます。コミュニティを重視することは引きこもり対策にもなっていきます。そうしたときにスポーツの力と価値が見直されることになるだろうと思います。
室伏 健康の定義が変わってきているのかもしれません。血液検査をして健康診断で異状なしといわれても、自覚症状として不健康ということがあります。内臓に疾患がなくても筋力が衰え立ち上がれないとか、肩こりがあるとか、腰痛がある、という状態は健康といえるでしょうか。これでは人生を楽しめません。こうした状態を運動によって改善し、階段が上りやすくなる、立ち上がりやすくなる、疲れにくくなるとなれば健康につながっていくと考えています。医者に診てもらって何も問題のないことがイコール健康だと考える人もいますが、そうではないと私は思います。自分で運動をして、身体の中に自然治癒の力があるわけですから、そういった力を目覚めさせることも大切です。健康とは何かという定義を含めてSport in Lifeのプロジェクトや各種研究によって解き明かしていきたいと思っています。
北出 高齢化が進む中で、健康寿命というワードが強調されています。寝たきりではない元気な身体で長生きするためには、やはり定期的な運動が不可欠だと思います。運動器は使わないと衰えますが、歩行が困難になると外に出かけるのが億劫になり、さらに関節の可動性が悪くなります。定期的に運動することで運動器の不具合も減り、脳の活性化や動脈硬化の予防にもなるため、医療費の削減にもつながります。
あとは、運動のメリットに関するエビデンスを国民に広く知ってもらい、それまで苦手意識をもっていた方が「やってみよう」と思える方法を考えていく必要があると思います。
橋本 共生社会の視点でいいますと、このような話を聞いたこともあります。難民キャンプを視察すると、キャンプに集まった人たちは部族、人種ごとに固まってほかの人たちとはまったく交流をもたない。そこにサッカーボールをひとつ置くと、まずは子どもたちが部族の垣根を超えて一緒にサッカーをする。やがて大人たちも輪に入り、コミュニティができあがっていく。これがスポーツの力だと。これをどのように解釈して社会に還元していくのか、というところがこれからの時代に求められているのではないでしょうか。
渡邉 身体活動が不活発になると子どもの発育、発達に悪い影響が出るのではないかと心配されます。子どもの身体活動を活発にするために、国や地方、学校がどのような取り組みを進めたらいいのでしょうか。
北出 最近では子どもの運動不足による筋力低下や肥満、骨粗しょう症が問題となっており、さらに若い女性は痩せているのに血糖値が高いというケースもあります。こうした問題を解決できる方法は、正しい食事と運動しかありません。
子どもの成長には適度な運動が不可欠ですが、現代の、特に都会では、子どもが安全に外で遊ぶ環境が少ないと思います。そうした中、テクノロジーを活用してインドアでもできるバーチャルスポーツや、限られたスペースでもできる都市型スポーツなどを行える環境があれば、閉じこもりがちな子どもたちの興味を惹き、遊びながら自然に身体を動かすことが可能になるかもしれません。
また、私がもうひとつ重要だと捉えているのが世代間交流です。
橋本 先生が部族間交流のお話をされましたが、世代を超えて楽しめるスポーツがあれば、地域のコミュニティにおける世代間交流も自然に生まれる可能性が高いと思います。孤独なお年寄りも小さな子どもと交流することで癒され、相乗効果も期待できるでしょう。
室伏 子どものときの運動習慣は非常に大切です。
2022年度の全国体力テストの結果は残念ながら小・中学校、男女ともに過去最低という結果になってしまいました。コロナ禍の影響もあるとは思いますが、全体的に体力が落ちて、肥満の子どもが多くなっています。こうした傾向に歯止めをかける必要があります。
まずは体育の授業を充実したものにしていくことが大事です。地域の受け入れ体制も含めて、あらゆる子が性別や障害の有無に関わらず運動できるような体制を整えていく必要があると思います。
渡邉 第3期スポーツ基本計画においても「スポーツによる地方創生、まちづくり」は重要な目標となっていますが、これからの地域におけるスポーツ推進、スポーツによるまちづくりにおいては、どのような視点が重要になるでしょうか。
橋本 スポーツの「する」「みる」「ささえる」「あつまる」という価値は、人びとの健康寿命の延伸に大きく貢献できます。スポーツ庁の「運動・スポーツ習慣化促進事業」のひとつである「医療と連携した地域における運動・スポーツの習慣化の実践」は、生活習慣病や疾患を抱える住民が、個々の状態に応じて健康的で楽しくスポーツに臨むことを促します。スポーツと医療の連携を図り、地域の活性化につなげていくことができればと思います。
また、スポーツを活用し、地域の社会課題の解決を促進することで、スポーツが地域・社会に貢献し、住民・国民の理解と支持をさらに広げ、スポーツ振興と地域振興の好循環が実現するでしょう。
東京2020大会開催に伴い、市民の間でスポーツ・文化活動が盛んになりました。スポーツチームはまちのコミュニティをささえ、教育に貢献しています。さらには地域に新たな経済効果を生み出し、公共施設活用のコンテンツとなるケースもあります。コロナ禍により、文化イベントやホストタウンによる交流も少なかったとはいえ、多くの気づきがあり、多方面にわたって市民生活が変化しようとしています。スポーツを活用することで、活力があり絆の強い社会の実現につながると考えています。
室伏 スポーツは、人と人との交流によって、地域の一体感や活力を醸成し、地域の活性化に寄与するものと考えています。スポーツ庁では、第3期スポーツ基本計画に基づき、スポーツを通じた地域活性化を推進しています。スポーツによるまちづくりの取り組みとして、スポーツを通じた地域の稼ぐ力の向上、交流人口の拡大や、誰もが出歩き体を動かし、スポーツができる社会づくり、住民の行動変容を目指す取り組みなど、先導的で優良な事例を表彰し、広く全国へ周知する「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰」を行っているところです。
笹川スポーツ財団が一緒に取り組まれている宮城県角田市では、かくだスポーツビレッジ(Kスポ)と道の駅を核として、明るく楽しく健康で活力あるまちの実現を目指し、交流人口の拡大や、スポーツ実施率の向上、道の駅の売上増など、スポーツによるまちづくりを展開していると伺っており、初年度に表彰させていただきました。
そのほかの受賞例を示しますと、徳島県三好市では、アウトドアスポーツツーリズムの拠点整備と持続可能な観光地域づくりを強みとして、地域内外の交流・関係人口の拡大へとつなぎ、将来的な移住者を増やすことを検討しています。また、秋田県大館市では、先導的共生社会ホストタウンとしての登録を契機に、誰もが住みやすいまちづくりを推進しており、ボッチャを活用した市民の健康維持や生きがいづくりなど、交流人口拡大による地域活性化に取り組んでいます。
こういった取り組みを、スポーツ庁が積極的に全国へアピールすることで、その地域だけでなく全国各地でスポーツによるまちづくりが広がっていくことを期待しています。
北出 医療分野における地域連携の例をあげると、専門治療ができる大きな病院と地域に密着したクリニックや地方病院のかかりつけ医がしっかり連携しながら、お互いに足りないところを補い合う方法があります。大きな病院は施設が整っていて高度な治療が可能ですが、一方では待ち時間が長く医者と患者の関係性が希薄になってしまうリスクもあります。地元のかかりつけ医では治療が限られますが、その分患者に寄り添ったきめ細かい治療ができます。
スポーツも同様に、基幹となる大きな団体・施設と地域密着型の施設がしっかり連携を取りながら、ニーズに応じてサービスを提供することが大事なのではないでしょうか。スポーツ庁をはじめとする省庁が確固たる骨組みをつくり、それを受けて地方自治体やスポーツ団体、地域のスポーツセンター、教育施設などがしっかりと連携し、地域の方々が安心し楽しくスポーツをできる場を提供していくことが重要かと思います。
スポーツの価値を未来に向けて

本座談会では、新型コロナウイルス感染対策としてマスクを着用しています。
渡邉 最後に、今後10年を見据えてスポーツ政策に携わる現場の方々、行政、研究者の方々に向けてメッセージをいただけますか。
橋本 成熟社会には経済の低成長、人口減少などの特徴があります。これまでと同じことをやるのではなく、スポーツの力で異なる文化や産業を結びつけ、新しい産業をつくり上げていくことが必要です。また、社会的資産を無駄なく最大限に活用する、つまり公立スポーツ施設だけでなく、学校体育施設・民間スポーツ施設など既存ストックをフル活用するためには、行政の縦割りの弊害を打破することも有効だろうと思います。
室伏 スポーツ基本法のもと、第3期スポーツ基本計画が動き出して1年になろうとしています。この10年の動きをみてもずいぶんと変わってきたと思います。さらに10年先ということですけども、私たちは未来の子どもにバトンをパスしていかなければなりません。今取り組んでいることが未来につながっていきます。そういう心づもりでスポーツに親しみ、心と体の健康に日々寄与できるよう、取り組んでいきたいと思っています。
北出 コロナ禍での東京2020大会は、多くの方に感動をもたらし、多様なレガシーが生まれたと思います。今後は第3期スポーツ基本計画に基づいて施策が実行されていくことで、スポーツは心身の健康維持や地域コミュニティの活性化など、優れた効果を発揮していくはずです。
ただ、部分的ではあるものの、いまだに指導者によるハラスメントやセカンドキャリアなどの問題が残っているようです。これらが迅速に解消され、健全なスポーツ環境が提供される世界になってほしいと心から願っています。
私たち医療従事者にできることは限られていますが、医学的な立場から研究のエビデンスやデータを提供し、政治を司る方々とも連携して、多くの方々が安全に楽しくスポーツができる社会づくりに貢献していきたいと考えています。