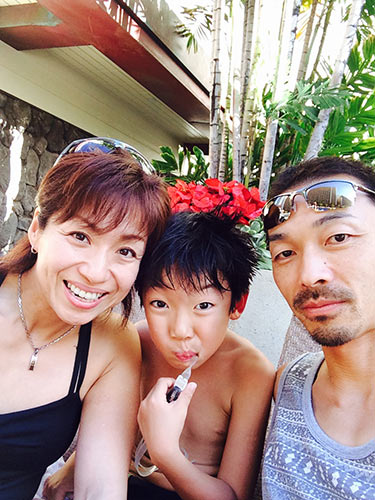選手としてストレスフリーだった大分車いすマラソンの予防対策
―― 2020年から新型コロナウイルス感染が拡大し、いまだに収束の見通しが立っていません。土田さん自身の生活にも大きく影響していることと思います。
一年前に新型コロナウイルスの感染拡大が一気に広がり始めた当初は、先行きが真っ暗な状態で、非常に困惑した時期もありました。ただ、必ずその先にはスポーツというものが世界で大きな力を持つということは思い描くことができていましたので、アスリートの一人として、その時に向けてしっかりと土台を作ろうということにシフトチェンジしました。

トレーニングルーム
―― 新型コロナウイルスの感染が世界に広がり、昨年3月24日にはIOC(国際オリンピック委員会)から東京オリンピック・パラリンピックを延期することが発表されました。その時、土田さんはどんなお気持ちになられましたか?
私は1994年リレハンメルパラリンピック(ノルウェー)から、夏冬あわせて7回のパラリンピックに出場してきました。しかし、"4年に一度の"パラリンピックが延期となるということは前代未聞のことで、当たり前ですが私自身にとっても初めてのことでした。
競技人生の中で最も予測不可能な事態でしたし、パラリンピックを一番の目標としてトレーニングに励んでいるものとしては、目の前の目標が突然なくなり、とても困惑しました。また、オリンピックと同様にパラリンピックは"4年に一度"というサイクルの中、1年1年プランを立てて積み上げていきますので、それが1年延期となったことによって2020年の東京パラリンピックに向けてのプランが崩れてしまいました。2021年に向けてプランを設定し直したり、目標設定することは簡単なことではありませんでした。というのも、私が競技をするうえで関わってくださっている方たちの人数が多いので、その方たちのスケジュールをすべて組みなおして、プランニングするというのは困難を極めました。
そうしたさまざまな問題にも直面するなかで、ただ東京オリンピック・パラリンピックが1年延期となったすぐ後の4月7日には日本では緊急事態宣言が発出されて自宅での自粛となりましたので、すぐに何かにとりかかるということはできず、まずは自分自身に目を向けるしかありませんでした。今振り返ると、それがかえって良かったのだと思います。1年延びたことを良い準備期間ができたというふうに捉えまして、まだ自分にないものをじっくりと追求できる期間にしようということで、自宅でできる範囲ではありましたが、しっかりとトレーニングに取り組むことができました。

大分車いすマラソン2020ゴールシーン
―― 5月25日に緊急事態宣言が解除されて以降は、少しずつスポーツ大会も開催されるようになりました。1年後に延期となった東京パラリンピックに向けて、土田さんはどこに照準を合わせていたのでしょうか。
私はパラトライアスロンと車いすマラソンの2競技での東京パラリンピック出場を目指しているのですが、どちらもまだ内定はしていませんので、とにかく選考レースに出場をしてランキングを上げるということが求められています。しかし、昨年は予定されていた選考レースがほぼすべて中止となり、私にとっては大きな痛手でした。
ただ唯一、「大分車いすマラソン」は11月に開催する方向で準備が進められていましたので、それを目標にしていました。大分車いすマラソンは、本来は「大分国際車いすマラソン」として1981年に世界で初めて車いすマラソン単独で開催されて以降、これまでは海外のトップランナーたちもエントリーする国際大会として開催されてきました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年に限っては日本人選手だけの国内大会として開催されたのですが、とにかくモチベーションをキープするうえでも、大分車いすマラソンに向かっていけたというのはとても大きかったです。
―― その大分車いすマラソンでは、女子のフルマラソンの部で若手の喜納翼選手に1分42秒の差をつけ、圧倒的な強さを見せての優勝でした。
喜納選手は30歳と若く、勢いのある選手で、同じ日本人として頼もしい存在です。世界で勝つということを考えても、やはり国内で切磋琢磨できる相手がいるのといないのとでは大違いですので、世界で戦えるランナーが女子車いすマラソン界に出てきたというのは、本当に嬉しいことです。なので、その喜納選手と戦えることを非常に楽しみにしていました。とは言っても、余裕があったわけではありません。自分自身が2年ぶりのフルマラソンのレースということもありましたし、出るからには世界トップレベルの走りをして一つでも世界ランキングを上げなければいけないと考えていましたので、自分自身にフォーカスしていました。そうしたなかで優勝できたことは、嬉しかったですし、大きな自信となりました。

土田和歌子選手(当日のインタビュー風景)
―― 大分車いすマラソンでは、どのような感染予防対策が行われていたのでしょうか。
大会運営側が、さまざまな知恵をしぼって、いろいろと工夫したなかで大会を開催してくれていることを感じ、とても安心してレースに臨むことができました。
まずはレース前日に大分県庁舎に設けられた選手受付で全参加選手がPCR検査を受けました。それも分散できるようにと、関東地区、関西地区、九州地区というようにブロックごとに時間が分かれていましたので、密になることなくスムーズに受付とPCR検査を受けることができました。PCR検査の結果も、その日の夜までには出ましたので、特にストレスを感じるようなことはなかったです。あとはレース以外のところではマスク着用が義務付けられ、外出もなるべく控えるようにと通達されていました。
私がとても細かいところまで気を使ってくださっているなと感じたのは、受付の時に一人ひとりにアルコール除菌のスプレーが配布されたことです。というのも、私たち車いすユーザーは常に車いすの車輪を手で触れていますので、例えば自宅では屋内と屋外とで車いすを乗り換えている選手がほとんどだと思いますが、自宅以外の施設ではどうしても屋外で使っている車いすでそのままホテルなどの屋内施設を利用します。衛生面では非常に懸念される部分なのですが、そういうところでも使えるようにと一人ずつにアルコール除菌のスプレーを配布されたのはとても助かりました。
それと大会運営という点では、開閉会式などのセレモニーはすべて中止となり、沿道での観戦も自粛していただくように周知されていましたので、実際にレース当日は沿道で観戦する人というのはほとんどいないような状態でした。もちろん、選手としてはとても寂しい思いをしたというのも事実です。これまで沿道からの声援のおかげで、苦しい時にも頑張ることができたり、背中を押していただけるというのはありましたので、そうした応援の力がゼロの状況でレースが行われるということが、こんなにも寂しく、これまでどれほど声援が大きな後押しとなっていたかということをしみじみと感じる大会でもありました。また、優勝した時も本来ならたくさんの人と喜びを分かち合える場面で、握手やハグのできないもどかしさはありました。ただ、今後は国際大会でも新しいスタイルのコミュニケーションが必要になってくるのかなと思いますので、いい経験になりました。
健康な体と生きる活力になるスポーツの存在

リオデジャネイロパラリンピック(2016年)
―― 新型コロナウイルスはいまだに世界中で猛威をふるっており、今年の東京オリンピック・パラリンピックの開催については、否定的な意見も少なくありません。そうしたなか、現役のアスリートとしてはどのように感じていらっしゃいますか?
当然、賛否両論あると思いますし、厳しい状況が続くなかでは否定的な意見が多くなるのは致し方ないことだと思います。
ただ、私自身の人生はスポーツとは切り離せられないものだと思っています。これまで私自身を成長させてくれたのもスポーツでした。
また、パラリンピックの存在を広く知っていただくためには、自分たちアスリートが歩みを止めてはいけないという思いが強くあります。とはいえ、今回のような事態はスポーツの力だけではどうすることもできませんし、何より人命に関わる問題です。人の命は最優先にしなければいけませんし、そもそも人の命があって、世界の平和が約束されて、初めてスポーツがあるのだと思いますので、オリンピック・パラリンピックが安心・安全が担保された大会でなければ開催の意義はなくなってしまいます。もちろん選手としては開催されることがベストですが、安心・安全がしっかりと約束されているということが、参加する選手としてもとても重要なことだと思います。
―― 特に、パラリンピック選手にとって"安心・安全"であることが非常に重要になります。
おっしゃる通りです。パラリンピックに参加する選手の中には、疾患を抱えている人もたくさんいますので、"安心・安全"を無視するわけにはいきません。パラリンピックの意義を考えても、そこはしっかりと向き合っていかなければいけない部分だと思います。

全国障害者スポーツ大会(1993)
―― このコロナ禍におけるスポーツの意義、アスリートの価値というのは、どのようにお考えでしょうか。
健康ということを考えると、スポーツは欠かすことはできないものだと思います。実際、私自身がそうでした。前回の2016年リオデジャネイロパラリンピックが終わった2カ月後の11月6日に、ニューヨークシティマラソン(アメリカ)に出場した際、レース途中で運動性の喘息を発症して途中棄権したんです。「もうスポーツはできないのかな」と思っていたのですが、帰国をして受診したところ医師から体質改善のために水泳を勧められました。それがきっかけで、パラトライアスロンに転向するという決断に至るわけですが、何より今も自分自身が健康でいられる、さらに競技者レベルの体を作れているというのは、水泳をしたおかげでした。これは一例にすぎませんが、実際に病気やケガを経験しているパラリンピック選手にとって、スポーツは生きていくうえで非常に重要な位置を占めていると思います。それは、パラリンピック選手だけでなく、オリンピック競技の選手もそうですし、高齢者にとっても言えることだと思います。
また健康面だけでなく、スポーツは生きる力にもなります。私自身がそうでした。17歳の時に交通事故に遭い、「もう一生、自分の足では歩くことができず、車いす生活になる」という宣告を受けた時のショックは非常に大きく、数日間は泣き続けました。しかし、そこからリハビリの一環としてスポーツを始めることによって目標もでき、多くの方たちとの出会いによってパラリンピックへの道につながっていきました。こうしたさまざまな部分に派生していくスポーツの価値というものを広く伝えていくことも私自身の役割だと考えています。
今も追い続ける初のパラリンピックで目にしたアスリート像

リレハンメル冬季パラリンピック(1994年)
―― 土田さんにとって初めてのパラリンピックが、1994年リレハンメルでした。アイススレッジスピードレースの日本代表として出場したわけですが、この競技を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
先ほども申し上げた通り、「車いす生活になる」ということに直面した時は、本当にショックでした。ただ私が入院していたのは、障がいのある人が社会復帰するためのリハビリ施設がある病院だったので、病室で寝ていると、廊下をカラフルな車いすで勢いよく駆け抜けていく姿が見えました。それを見て、「あぁ、車いすでこんなにアクティブに動けるんだ!私も早くあのかっこいい車いすに乗って社会復帰をしたい!」と思えたことで、割と早い段階で自分自身の障がいを受け入れることができました。そういう意味では、環境に恵まれていたと思います。もし、入院してすぐにアクティブに動いている方たちを目にすることがなければ、車いすでの生活がイメージできず、長い間ふさぎ込んだままだったかもしれません。そんなふうに環境にも助けられて、リハビリでスポーツに取り組むようになり、パラリンピックを目指す道へとつながっていきました。
実は最初は、アイススレッジスピードレースではなく、小学生の時にはミニバスケットボールを経験したこともあって車いすバスケットボールをやろうかなと考えていました。入院していた病院には体育館もありまして、そこで社会復帰を目指す患者さんたちが車いすバスケをしていたんです。それを見て「かっこいいな」と思っていました。また一方では、担当医からの紹介で知り合った障がい者スポーツ指導員の方の勧めで、入院した翌年の1993年には、徳島県で開催された「全国身体障害者スポーツ大会」(以下、全スポ)にパラ陸上の選手として、100mとソフトボール投げの2種目に出場しました。両種目ともにメダルも取れたのですごく楽しくて、「陸上もいいな」と思っていました。ただ、車いすバスケのクラブチームから勧誘されていたので、全スポ後に「やっぱり車いすバスケにしようかな」と女子のクラブチームに加入するつもりで、練習に参加していたんです。
そうしたところ、5年後の1998年に開催が決定していた長野パラリンピックの正式種目の一つで、それまで日本人は一人も選手を派遣したことがなかったアイススレッジスピードレースの選手を育成しようと長野県が主催した講習会に、私たちのチームが招待を受けまして、私も参加することになりました。その講習会に、アイススレッジスピードレースの発祥の地でもあるノルウェーの講師がいたのですが、19歳と若く体力もあった私が一人で、スレッジに乗ってクルクルとスケート場を回っているのを見て、「彼女は体も柔軟だし、素質があるよ」と言っていただいたようなんです。それで講習会後、東京に戻った時に日本の競技関係者から連絡がありまして、「リレハンメルパラリンピックに出場してみませんか?」というオファーを受けました。でも、大会は3カ月後だったんです。正直、ただ講習会で一度、見よう見まねでやっただけで、何も知らないのに本当に出られるのか不安しかありませんでした。ただ、私を指導してくださったコーチが、とても情熱のある方でしたので、一緒に試行錯誤しながらトレーニングに付き合ってくださいまして、なんとかリレハンメルパラリンピックの舞台に上がることができました。
結果はもちろん惨敗でした(笑)。世界との実力差を目の当たりにして、恐怖心を抱いてしまって、「早く日本に帰りたい」とばかり思っていました。ただ、得られたものは小さくはありませんでした。アイススレッジスピードレースには、地元のノルウェーから40、50代の選手が何人も出場していて、そのうち3人の選手が、100、500、700、1000mの全4種目の表彰台を独占してしまいました。100mと500mで金メダルを獲得した当時49歳のBrit Mjaasund Oejen選手は、1980年ヤイロパラリンピック(ノルウェー)ではクロスカントリーで2個の金メダルを獲得し、リレハンメルパラリンピックではアイススレッジスピードレースのほかにアイススレッジホッケー(現パラアイスホッケー)にも男子に交じって出場し、銀メダルを獲得しています。700mで優勝した当時50歳のRagnhild Myklebust選手は、1998年長野パラリンピックではクロスカントリーで4冠を達成。その後2002年のソルトレイクシティパラリンピック(アメリカ)まで出場し、冬季パラリンピックでは最多となる27個のメダル(金22、銀3、銅2)を獲得した選手です。
彼女たちはみんな筋骨隆々の、まさにアスリートの体をしていたんです。そんなストイックなアスリートの体を初めて間近で見て、「障がいがあっても、この年齢でも、トレーニングを積めば、こんなにもアスリートの体になれるんだ」ということを知りました。そして大会期間中にも海外選手のストイックな食事やトレーニングを見て、「パラリンピックとは、これだけやらないと勝てない世界なんだな」と思いました。リレハンメルでの彼女たちの姿は今でも鮮明に覚えていますし、その後の競技人生にも大きな影響を与えてくれたと思います。私自身、46歳となりましたが、今もリレハンメルパラリンピックで見た選手たちの姿を追いかけているようなところがある気がしています。苦しくてくじけそうになった時には、彼女たちの姿が頭に浮かび、また頑張ることができるんです。

長野冬季パラリンピック(1998)開会式・日本選手団入場(前列左から3人目)
―― リレハンメルパラリンピックから帰国後は、すぐに気持ちを切り替えて、1998年長野パラリンピックに向かっていったのでしょうか。
すぐに長野パラリンピックに気持ちを向けられたわけではありませんでした。というのも、リレハンメルパラリンピックでは100mのレースで転倒して、自分の実力を出し切ることができなかったんです。もちろん、たとえ100%の力を出し切ったとしても勝てなかったとは思います。ただ、アクシデントによって発揮できなかったことで、この競技が自分に向いているか向いていないかと考えた時に、「アイススレッジスピードレースではなくてもいいんじゃないのかな」と思ったんです。ですので、リレハンメルパラリンピックから帰国してしばらくはまた車いすバスケのチームに戻って練習していました。ところが、数カ月も経つと、沸々と「次の長野パラリンピックでリベンジを果たしたい」という気持ちがわいてきました。それで、アイススレッジスピードレースで長野パラリンピックを目指すことを決意しました。