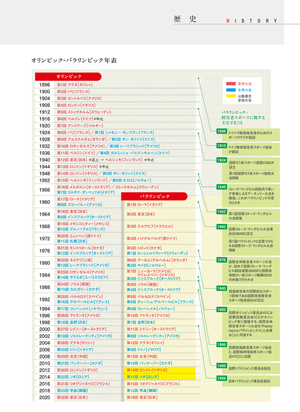身も心もパラリンピックに捧げる日々

2015年 リオパラリンピック
テストイベント・トライアスロン
―― 年が明けてますますお忙しいのではないですか?
忙しさは刻々と増し、2020年まで息つく暇はないと覚悟しております。
―― 少し前まで、2020年東京大会については盛んに言われていたものの、直近のリオデジャネイロ大会のことは忘れられがちでした。それが2016年に入って突如、「リオでのメダル目標獲得数は何個!」などとやかましくなってきましたね。
大会に向け、前々から盛り上げたいというのは我々の願いの常なんですが、パラリンピックは開催年にならないとなかなか盛り上がらないものです。メダルの数とか、選手の活躍予測がなされるのもやっぱり当然のことで、我々のほうでも目標を立て、そこに近づけるよう選手、競技団体、関係者一同でがんばっていきたいと思います。
―― 障がい者スポーツの世界に足を踏み入れられたきっかけはどんなものでしたか?
ちょっとお恥ずかしい話ですけど、自発的に始めたのではないのです。2011年の暮れに、日本障がい者スポーツ協会と日本パラリンピック委員会(JPC)の会長に就任した鳥原光憲さんに「ちょっと手伝ってくれ」と言われて。鳥原会長とは仕事でもプライベートでも非常に親しい間柄でした。それで「ちょっとの手伝い」のつもりで始めたら、実際はとんでもない……(笑) 1970年から勤め上げた日本郵船の現役を4年前に退いてからは、こちらに身も心も捧げているという感じで、楽しくやっています。
海運業から突如、障がい者スポーツの世界へ
―― 愛知県半田市のお生まれで、名古屋大学ご出身。子ども時代からのご自身のスポーツ歴は?
高校までスポーツとは縁遠かったのですが、足が速かったこともあり、大学からはスポーツをやってみようとスキー部に入りました。学校に行くよりスポーツをしていた時間のほうが長かったです。
―― 日本郵船に入ったのはどのような動機からですか?
当時は青田買いの走りで就職活動期間がかなり早まっていて、大学3年生の終わりに真っ黒けな顔でスキーの合宿から帰ってきたら、周りの同級生はほとんど就職活動が終わっていたという状況でした。そこにタイミングよく出会ったのが日本郵船だったんです。日本郵船では社員のスポーツ参加をとても奨励していて、ボートやラグビーやテニスに親しみました。会社に仕事をしに行ってるのか、遊びに行ってるのかわからないくらいでした(笑)

2012年 ロンドンパラリンピック 田口亜希
―― お仕事の内容は?
入社3年目でアメリカ勤務になり、その後4年間をアメリカの地方の町やニューヨークで過ごしました。当時はちょうどコンテナ船が始まったころで、港から陸上にコンテナが輸送されるようになり、アメリカの鉄道について調べる任務が与えられて船よりも鉄道について詳しくなりましたね。また突然アメリカのとある町に放り出されて、外国人ばかりの所で年月を過ごしたという経験は後で大きな糧になりました。
―― 当時の障がい者スポーツというのは記憶にありますか?
実際に自分が競技を観たのは、2012年のジャパンパラ競技大会が初めてでした。そして2012年のロンドンパラリンピックではJPCの役員として全期間競技をつぶさに観て、大変な衝撃を受け、もっと早く出会っていたら自分の人生は変わっていたかもしれないと思いました。日本郵船時代にも、社員に射撃のパラリンピアンの田口亜希さんがいらして会社でもサポートをしていたということがあったのですが、近年障がい者スポーツに触れるようになって、改めて彼女のすばらしさを認識しました。
障がい者スポーツには健常者の意識を変える力がある

グットマン博士
―― 障がい者スポーツの魅力をどこに感じているのですか?
もともとパラリンピックは、20世紀中ごろに、その後“パラリンピックの父”と呼ばれるイギリスのグットマン博士が、手術ではどうにもならない傷病兵の脊髄損傷者のリハビリや社会復帰にスポーツが効果的であることを発見して始めたものです。障がい者のためという意味合いが主だったわけですが、我々が今期待しているのは、障がいのある人がスポーツをすることによって、我々健常者の意識を変えてくれること。
「障がい」というのは、障がいのある人の側ではなく、社会の環境とか、障がいのある人を見る人々の目や心にあると思うんです。そもそもパーフェクトな健常者などいませんね。
視覚障がいのあるパラリンピアンの河合純一さんは、「目が見えないのは不便だけど不幸ではありません」とおっしゃいました。「私は目が見えないだけで至って健康です。精神も健全です」と。確かにそうですよね。
「あなたのほうこそお酒の飲み過ぎや糖尿病は大丈夫ですか、物忘れはしませんか、精神は病んでいませんか……」と、きっとそういうことなんです。おそらくアスリートの人たちは、自分を障がい者だとは思っていない。ほかの機能でカバーできるし、人生を生きるうえでは別にどうってことありませんってことなんですよね。ビジネスでいろんな修羅場を乗り越えてきたつもりでしたが、私の修羅場なんてアスリートに比べればたいした修羅場じゃないなと思ったものです。
―― 障がい者スポーツは、健常者のスポーツよりも見る人に与えるエネルギーがずっと大きい気がしますね。
人間の潜在能力はすごいなってことですね。たまに現れる天才は別として、我々は一般的に平均30%くらいの機能しか発揮していない感じがします。どこかひとつの機能が失われることによってほかの機能の潜在能力が覚醒するんですね。
日本の障がい者スポーツの「ビジョン」を具体化

2008年 北京パラリンピック 河合純一
―― 日本障がい者スポーツ協会での活動については、当初どんなイメージを持っていましたか?
最初は年に5、6回開催される理事会に出ていればいいのかなと思っていたのですが、いざ始めてみたら、さにあらず。まず、職員とともに「活力のある共生社会」という日本障がい者スポーツ協会のビジョンの具体化に取り組みました。その過程で、やらなきゃいかんことはたくさんあるなと感じました。
―― 想像していた状況と違いましたか? どんなところが足りないと?
まずビジョンをつくるという意識が欠けていた。国からの予算の分配のあり方を、具体的な形でみんなで共有できていなかった。そこで、鳥原さんのリーダーシップのもとでビジョンづくりを始めましたが、最初は、ビジョンの必要性を感じる人は少数でした。
みなさん非常に情熱をもってアスリートのサポートなどをやっていたのですが、先を見据えて新しいことにチャレンジする姿勢が不足していた。サポートを次にどう進めるか、外へどう発信するか、国とどう関わり、周りにどう応援してもらうかといったノウハウがなかった。個々の人たちのすばらしい熱意を、統一されたビジョンのもとで組織として形にしていくことが必要だったんですね。
最初に夢があり、ビジョンが生まれ、アクションプランがつくられ、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルで回す。この、企業に必要なプロセスをみんなで実行していくには、意識改革がまず必要でした。
―― どのようにして意識改革を?
それはもう、実際に障害を取り除きながらやって見せるしかないですね。「人がいない」なら人を引っ張ってくる、「お金がない」なら「お金ならなんとかする」といったように。幸い2020年に向けていろんなことへの賛同者が増えてきているので、どんどん進めていきたいと思っています。

1964年 東京パラリンピック開会式
―― 障がい者スポーツに関わる法体制なども整備されてきました。
スポーツ基本法にスポーツはすべての人々の権利であることが明記されたように、流れはできつつありました。ただ実際には管轄が厚生労働省であったので、「障がい者のための福祉」という考えが優先されたのではないでしょうか。ビジョン作成過程でスポーツ政策の一元化が強く打ち出されたのでそれは非常によかったなと思いますが、障がいのリハビリからスポーツへという流れはシームレス(切れ目がない)に繋がっていなければならないので、政策の一元化によってその部分が切れないよう、地方との連携もうまくやりたいなと思っています。もともと中央と地方には連携不足の問題がありますので、注意をはらってやっていかないといけません。
インクルーシブな
社会実現のための社会運動
―― ビジョンをつくるうえで大切にしたことは?
何か大きなことをしようというときには、さまざまな人がさまざまな目的を持って集まってきます。そのときに、ベクトルを同じにするための拠り所がビジョンや目標なんですね。
そこでまず、「アスリートを中心においた障がい者スポーツ」を人々に理解してもらって、それによって「人々の意識を変え、活力ある共生社会をつくっていく」。そのために私たちはやってるんですよということをはっきりさせました。
組織の維持やお金も必要ですが、究極の目的はこういうことなんですよと。オリンピックには「より平和な世界を」という目標がありますが、いつしか商業主義に傾き、勝つためには手段を選ばずみたいな流れもできてしまっている。

2012年 ロンドンパラリンピック佐藤真海
パラリンピックはもっと社会に近いところの活動というか、いわばスポーツという切り口で社会を変革していくという壮大な社会実験をしているようなものです。
障がい者スポーツというのは、思想や宗教を超えて意識改革ができる、明るく楽しく人々を巻き込みながら行える社会運動なんですね。
その原点にはアスリートのパフォーマンスがあります。それを見るだけで、人々の意識が簡単に変わるんですね。私がそうだったように。
―― 山脇さんは2013年に、日本人として史上2人目となる国際パラリンピック委員会(IPC)理事に就任されています。世界でもこのような見方は共通ですか?
IPCでは、「アスリートに最高の環境を与えて最高の力を発揮させ、人々の意識を変えてインクルーシブな共生社会をつくろう」ということが日本よりもはっきり打ち出されています。