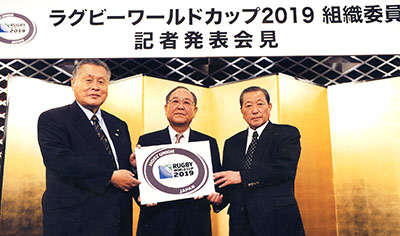眞下昇氏(インタビュー風景)
―― 群馬県立高崎高校といえば進学校として知られていますが、ラグビー部も北関東では有数の強豪校でしたね。
それこそ県内では先輩たちの時代から引き継がれた連勝記録は101にものぼるほど、無敵を誇っていました。県内で常に雌雄を争うライバル校である前橋高校と毎年行われるスポーツの定期戦では、高崎高のラグビー部が強すぎたために、代わりに他の競技の選手がラグビーチームを編成して戦いました。一方私たちラグビー部員はそれぞれ他の競技に駆り出されていたのですが、私は陸上部の800mが人数が足りないからというので、「走ればいいんでしょ?」という軽い気持ちで手を挙げたことがあったんです。ペース配分なんてものは全く知りませんから、号砲とともに全速力で走り始めたので、最初はダントツのトップでした。ところが、残り200mあたりからガクンとスピードが落ちて、どんどん後ろから抜かれていったんです。「おかしいなぁ。なんで足が動かないんだろう」と思いながら走りましたけども、最初から全速力で走ったらエネルギーなんか残っていないのは当然ですよね(笑)。結果は4、5着だったと記憶しています。
―― 眞下さんが在籍していた頃、高崎高は全国大会ではどのくらいの成績を収められていましたか。
私の頃は、まだ全国高校ラグビーフットボール大会が花園ラグビー場ではなく、西宮球場で行われていた時代だったのですが、私が2年の時の大会では、秋の第10回国民体育大会(国体)で優勝しました。全国大会では準決勝で保善高校(東京都)に敗けました。3年の時は国体には行けなかったのですが、全国大会では準々決勝まで行きました。

筑波大学(旧東京教育大学)ラグビー部の集合写真(上から2列目、左から8人目)
―― ポジションはバックスですか。
高校時代はセンター(バックスの中心に位置し、攻撃時には突破役となり、守備ではタックルで相手の攻撃の芽を摘むポジション)をやっていました。大学に入ってからはスタンドオフ(パス、キック、ランでゲームをコントロールし司令塔の役割を担うポジション)でした。というのも、入学してすぐにスタンドオフの先輩がケガをしてしまって、「誰もいないから、オマエやってくれ」ということで急きょやることになったんです。
「引退後もラグビーに携わりたい」とレフリーの道へ

日本選手権に進出した躍進目覚ましい筑波大ラグビー部(2015年)
―― 高校卒業後、いわゆる古豪ではあっても、決して圧倒的に強いわけではなかった東京教育大学(現筑波大学)に進学されました。強豪校に進むことは考えなかったんですか。
3年の時の担任の先生が東京教育大出身で勧められていたんです。でも、当時は1月15日に秩父宮ラグビー場で全国高等学校大会に出場した関東周辺の高校チームによる出場記念試合が行われていました。そのために本格的な受験勉強は1月16日からスタートするわけです。それで「ずっとラグビーばかりやってきて、8科目も試験がある国立大学なんてとても無理だから、3教科の私立大学に行きたいと思っています」と先生に言ったところ、「ダメだ。東京教育大を受けろ。今から勉強すれば砂漠に水が吸い込まれるごとく覚えられる」と励まされた。1学年上の先輩で東京教育大に行った人も、なぜか私に「受験しろ」と勧めてきまして、それでもう受けるしかなくなってしまったというわけです。先生からは「1教科でも0点を取れば、他がすべて100点でも落ちるからな」とプレッシャーをかけられまして、しかも当時は浪人なんて考えられませんでしたから、「試験に落ちたらどうなるんだろう」と不安しかありませんでした。ですから「これは、大変なことになった」と、もう毎日徹夜で勉強しました。でも、そんな無茶なことができたのも、ラグビーで体を鍛えていたおかげだったかなと思いますね。
―― 当時の東京教育大のラグビー部は強かったんですか、それとも…。
まったく強くはなかったですよ。高校時代は試合をすれば勝つものだと思っていたのが大学では常に敗戦ばかりでした。部員の中には全国大会出場経験者はほとんどいませんでした。当時、関東の大学でラグビー部は17校ほどだったと思いますが、その内の"中の下(ちゅうのげ)"くらいでした。

ドットウエル・ラグビー部時代
―― 大学時代の一番の思い出といえば、何でしょうか。
大学時代はケガが多くて、部に貢献出来なかったですね。毎年夏には山中湖で15日間の合宿があったのですが、1年の時にはその合宿中に右肩を痛めたんです。そしたら40度の発熱も引き起こして、その時は何が原因かわからなかったのですが、病院で診察してもらったら骨髄炎を発症していました。抗生物質で熱を下げてから、骨を削る手術をしたのですが、結局完治するのに6カ月ほどかかりまして、1年のシーズンはまるまる棒に振りました。2年の時は、シーズン半ばの試合で味方プレーヤーに後ろの死角から左膝に飛び込まれて左膝の前十字靭帯断裂という大けがをしました。3年の時には肋骨を3本ほど折りまして、絆創膏を巻きながらプレーしていました。まともにプレーできたのは最後の4年の時だけでしたね。

エリスクラブ時代の韓国遠征(右から2人目/1969年)
―― 大学卒業後は外資系商社のドットウエルに入社されて、同社のラグビー部でプレーすると同時にクラブチームの名門「エリスクラブ」でもプレーされています。そのエリスクラブでは1969年にキャプテンとして韓国遠征を経験し、それを最後に現役を引退。その後レフリーになられていますが、レフリーをやろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
すっかりラグビーに魅了されていたことと、現役時代にお世話になった方々に恩返しをしたいということで、現役引退後も何かしらのかたちでラグビーに携わっていたいという気持ちがあったんです。それでエリスクラブでプレーしていた時に、同じクラブチームの「エーコンクラブ」のキャプテンでレフリー委員会の副委員長を務められていた方が、韓国遠征から帰国して現役引退を表明した際、「これからはレフリーをやりなさい」と。実はそれ以前に社会人リーグ同士の試合では、自分のチームの試合が終わると、次の試合のレフリーを務めていたりもしていたので、迷うことなく「はい」とその場で返事をしました。それまではライセンスなしで見様見真似でやっていたのですが、現役引退後にレフリー資格試験を受けまして、1972年にB級ラインセンスを取得して関東ラグビーフットボール協会主催の試合のレフリーを務めるようになりました。その後、経験を経て推薦されて日本ラグビーフットボール協会のA級ライセンスを取得しました。
日本ラグビーの大改革断行

「トップリーグ」への移行を伝える2003年1月12日付けの朝日新聞記事
―― さて、来年にはアジアで初のラグビーワールドカップが開催されます。眞下さんは招致の段階から携わってこられましたね。
日本代表が1999年にウェールズで行われた第4回ラグビーワールドカップに臨んだ際、OBとはいえオールブラックス(ニュージーランド代表の愛称)から何人か日本代表チームに加わっていたにもかかわらず、海外チームに歯が立たなかったんです。さらにパワーアップしていかないと、日本は海外に肩を並べることはできないということが示されたわけですが、ちょうど世界的にはアマチュアリズムが撤廃されてプロ化の道に突き進んでいる最中でした。特に欧州や南半球のチームは完全にプロ化の道を進んでいて、日本とは歴然とした差が開いていました。ですから、日本もプロ化に移行していかなければいけないと言われていたのですが、アマチュアリズムが根強かった日本ラグビー界はなかなかプロ化には進みませんでした。しかし私は、プロ化は避けては通れないと思っていましたので、代表チームに海外からプロの選手を入れるか、あるいは国内にプロのチームを作るしかないと思っていました。それで日本ラグビーフットボール協会の当時専務理事を務めていた白井善三郎さんに「日本代表に海外の選手を積極的に入れてはどうでしょうか」と提案したこともあったんです。しかし、当時の協会には海外から選手を呼ぶだけの資金がなかったんですね。それでもなんとか日本代表強化をしていかなければいけないということで、前述の白井専務理事の号令の元、日本協会の大改革を掲げました。そして当時の日本協会理事4名に改革を指示されたのです。私には大会の運営でした。私はそれまで大学と社会人の優勝チーム同士で争われていた日本ラグビーフットボール選手権を発展的に解消し、2003年からは(※55年続いた全国社会人大会を発展的解消しトップリーグを創設)トップリーグの順位決定戦としました。真の強い選手同士で競う場を設け、また海外から選手たちを入れることで、世界と互角に戦える力を普段から身に付けられるような環境を作るというのが目的でした。2001年に協会会長に就任した東大ラグビー部OBの町井徹郎氏には協会の役員制度を刷新し、慶大ラグビー部OBで国際ラグビーボード(IRB:2014年に「ワールドラグビー」(WR)に名称変更)理事でもあった堀越慈氏がマーケティング改革でスポンサー集めに奔走し、日本代表監督も務めた早大ラグビー部OBの宿澤広朗氏が日本代表チームの強化を担当しました。それぞれの専門分野での改革をしていったんです。

眞下昇氏(インタビュー風景)
―― そうした大改革の中で、ラグビーワールドカップを招致しようという話はどのように盛り上がっていったんですか。
今年からトップリーグが開幕するという2003年のお正月に、私がある新聞社のフォーラムに招かれたことがあったんです。その時、その新聞社の記者がこう言ったんです。「眞下さん、トップリーグを立ち上げるというだけでなく、将来的にはラグビーワールドカップを開催したいという話もされたらどうでしょうか」と。それで私はフォーラムで「9月からトップリーグが始まります。そしてゆくゆくはラグビーワールドカップを日本に招致して、日本ラグビー界、日本スポーツ界を活性化させていきたいと思っています」という話をしました。それがきっかけとなって、2011年大会の招致活動へとつながっていきました。

小泉純一郎首相(当時)(中央)、河野一郎氏(右)と
―― その後、招致活動がスタートします。この経緯を教えてください。
まずは2003年に、森喜朗元首相と日本ラグビーフットボール協会の当時の町井会長と私の3人で、国際ラグビーボードのシド・ミラー会長(当時)に正式にラグビーワールドカップ招致を申し入れました。その後、帰国してすぐに招致委員会を発足しまして、森氏に会長に就任していただき、そして当時日本ラグビーフットボール協会の専務理事をしていた私がその招致委員会の責任者ということで委員長を務めることになりました。

2011年ラグビーワールドカップ招致活動。IRB(国際ラグビーボード)ミラー会長(前列右から2人目)、森元首相(招致委会長、前列左から3人目)。後列左から2人目が眞下氏
―― 当時、招致に関わった人たちに話を聞きますと、森会長の存在がたいへん大きかったといわれています。
おっしゃる通りです。私が森氏のすごさを改めて感じたのは、2011年大会の招致でニュージーランドに2票差で負けた時のことです。私自身は、もちろん負けたことへの悔しさはありましたが、それでもロビー活動をしてきた中で、たくさんの海外のレフリー仲間に助けてもらいましたし、また投票で負けた日も「ノビ(眞下氏の愛称)、次だよ!」と励ましてもらいましたので、「よし、次こそ勝つぞ!」というふうに思っていたんです。
すると、さすが森氏は行動が速かったですね。投票翌日にはミラー会長の元を訪れたんです。会長としては森氏を慰めるつもりでいたと思うのですが、森氏はミラー会長にズバッと問題を指摘されました。というのも、当時はラグビー先進国であるファウンデーションユニオン(イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス)はそれぞれ理事が2人いましたので、それぞれ投票権を2つ持っていたわけです。ところが、日本を含むその他の4カ国は後進国で理事が1人でしたので、1票しか持っていません。それではファウンデーションユニオンの有利な投票結果になることは誰の目から見ても明らかでした。それで森氏は「仲間うちでボールを回しあっていては、いつまでたってもラグビーはグローバルなスポーツにならないですよ」と、ものすごい剣幕でおっしゃいまして、ミラー会長もその勢いに完全に押されていました。あの時、森氏がはっきりと主張してくださったことが、2019年大会の招致の成功につながったことは間違いありません。