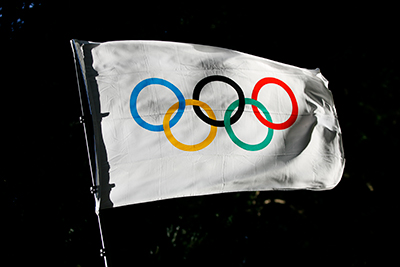時間を要した色、大きさ、生地の選択。特に難しかったのは「日の丸」

組織委競技部の職員と(後列左から二人目が吹浦氏)
―― 組織委の国旗担当は、何人体制だったのでしょうか?
基本的には専門家のような立場は私一人です。ほかに管理面や掲揚などで手伝ってくれるスタッフは何人かいましたが、海外の国旗のことなんて知らない人ばかりでしたから、責任はすべて私にありました。
―― 最初にどんなことから着手したのでしょうか?
まずは、参加する可能性のある国のリストを作りました。それから、世界の国旗に関連する資料をかき集めて、それぞれ比較することから始めたわけですが、巣鴨のいささか怪しげな旅館に5泊ぐらいして、だだっ広い畳の部屋に、16冊の内外の資料を広げて、色は何番の色票を使っているのか、すべてリストに書き込んでいきました。ところが、例えば同じ「青色」でも、国や資料によって、さまざまな「青い色」があるんです。
―― 国旗の色は、明確に決められているんでしょうか?
さまざまですが、例えばアルジェリアの国旗は、バックが緑と白に、赤の星と月のマークが付いているデザインなのですが、緑と赤については光の周波数で決まっていて、非常に厳格なんです。ただ、それをすべて守ろうとすると、膨大な色の種類になってしまいます。そこで、青色だけは4種類に分けて、あとの色はすべて1色で作るという方針をかためるまでに、10カ月ほどの時間を要しました。最近では緑や黄色も2段階ぐらいにしていますが。

リオデジャネイロオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得し日の丸を掲げる日本チーム
(2016年)
―― 本当に大変な作業で、苦労も多かったと伺っていますが、なかでも最も吹浦さんの頭を悩ませたのは、日本の「日の丸」だったそうですね。
はい、そうなんです。何が一番苦労したかというと、日の丸の「赤色」を決めることでした。日の丸の「赤色」については「紅色」ということしか法的根拠がないのです。「じゃあ、一体、『紅色』とは何ぞや」というところから考えていかなければいけませんでした。
そこで、日本色彩研究所と、資生堂研究所の協力を得て、まず、500枚の日の丸を一般家庭からかき集めました。当時は、どの家にも必ず国旗があって、祝日には玄関の前に掲げられていましたから、一軒一軒まわりまして、「すみません。組織委のものですが、ご自宅にある国旗をいただけませんか」とお願いしにあがったんです。もらうだけでは申し訳ないですから、こちらが作った日の丸と交換するという条件で。そうしてかき集めた日の丸を、日本色彩研究所が分析して、「色見本表」というものを作ってくれました。はみ出している色票は除外して、平均値を求め、それを日の丸の「赤色」とすることに決めたんです。それを、本来は少しずつ異なる「赤色」であるアメリカやイギリスの国旗にも使い、各国のNOC(オリンピック委員会)に送って承認を得ました。
―― ということは、日の丸の「赤色」を決めたのは、吹浦さんだったわけですね。
正直言って、日の丸の「赤色」を決めるなど、恐ろしかったですよ。組織委の幹部も「どこかしかるべきところから承認を得なさい」と言うわけです。ところが、官房長官のところに持っていったのですが、「勘弁してくれ。そんなことは、とてもうちでは決められないよ」と言われました。ですから、最終的には私が「これが日の丸の赤です」と決めるほかありませんでした。

日の丸のフェイスペインティングで応援する外国のサポーター
―― 終戦から20年近く経っていたとはいえ、やはり当時はまだ「日の丸」に対してのイメージというのは、重々しいものがあったのではないでしょうか。
その通りです。今では、サッカーなどの試合では「フェイス・ペインティング」で日の丸を顔に描いたりしていますが、当時は敗戦の後遺症というか、非常に畏れ多いもので、敬遠する雰囲気が残っていました。ですから、そのイメージを払拭しようと、当時の若手グラフィック・デザイナー永井一正さんほかお二人が日宣美展で「新しい日の丸の提案」というものを行ったんです。これは、縦と横の比率が2対3で、円の大きさが縦の3分の2にしたものでした。そうすると、これまでの日の丸と随分イメージが変わって、新鮮だということで、多くのメディアが推薦してくれたんです。そこで、丹下健三さんや亀倉雄策さん、勝見勝さんといった方たちがおられた組織委のデザイン委員会が検討した結果、採用ということになりました。
実際、オリンピックの前年に行われたプレオリンピックでは採用されました。ところが、毎日新聞が一面に「組織委、国旗を変更」という見出しで記事を載せたものですから、有名な右翼の親分がやって来たんです。組織委の幹部の人たちは、みんな恐れおののいてしまったのですが、若かった私は、ここでも怖い者知らずだったんでしょうね。帰り際、お見送りするといって付いて行き、巻き尺を手に「そちらの日の丸を測らせてください」と言ったんです。縦の5分の4近くはありました。そしたら、「やかましい!」と言って、砂煙を挙げて立ち去っていってしまいました。結局、東京オリンピックでは3分の2の日の丸は使用されませんでしたが、34年後の長野オリンピックでは、背景が雪と氷の白でしたから、日の丸が少し大きい方が見やすいだろうということで、念願の3分の2の日の丸を掲げさせていただきました。

長野冬季オリンピック開会式で入場する日本選手団(1998年)
―― 色、大きさのほかにはどんなことを決めなければいけなかったのでしょうか?
国旗に使用する生地選びです。強度で言えばナイロンなのですが、少し安っぽく見えてしまうんですね。それで、ナイロンとウールとエクセランの3つの生地で、紋章のついたグアテマラ、スペイン、メキシコの国旗をつくり、15日間、国立競技場の上にさらすという検証を行いました。そうしたところ、9日目に台風の余波で、暴風が吹き荒れ、ウール(大同毛織)が破れてしまい、そして11日目には雨でナイロン(東レ)は、「染が泣く」と言うのですが、色が流れてしまいました。それで結局、ウールの品の良さと、ナイロンの強度を兼ね備えているということで、まだ外国旗の製造では実績がほとんどないのですがエクスラン(東洋紡)を使用することになったんです。
―― 「エクスラン」とは、アクリル繊維のことでしょうか?
そうです。当時、東洋紡が開発したばかりの新しい繊維でした。実は、このエクスランにも反対の声があったんです。「神聖な国旗に化学製品を使ってもいいものか」と。歴史を紐解けば、それ以前に化学繊維を使用したのは、1936年のベルリン・オリンピックだけでした。しかし、実際に検証した結果ですから、私は「化学製品を使ってもいいのでは」と強く推しました。最終的にはエクスランを使用して正しかったと思います。以後、日本での大判の旗はエクスランで定着しました。

吹浦忠正氏
―― そして、いよいよ国旗の製作に入ったわけですね。
はい、そうなのですが、製作においても、例えば「染める」のか「縫う」のかでは全然異なりますし、縫うにしても糸の色や、きれいに見えるような縫い方など、本当に苦労は絶えませんでした。あまりにも縫い糸が強いと生地が切れてしまいますので、縫い糸がやや弱めにしておかないと強度が保てないということも途中でわかりました。
―― 特に縫い方が難しかったのは、どこの国旗だったのでしょう?
それこそ、日の丸です。国立競技場の電光掲示板の上にあった国旗は、縦3m×横4m50cmと、非常に大きなものでしたが、まずは白色の原反にハギを入れて3段に縫い合わせ、その真ん中を丸く切り取るんです。そこに赤色の生地をはめこむようにして縫い合わせていくのですが、円が歪まないように縫うのは本当に難しい技術でして、現在では悲しいことに、日本ではそれをできる職人が皆無に等しいと思います。それほど難しいんです。

東京オリンピック開会式で入場する日本選手団(1964年)
―― 当時は高度な技術をもつ職人がたくさんいたんですか?
はい、何十人といました。というのも、まだ戦後20年も経っていない時期ですから、戦時中に日の丸や旭日旗を作っていた職人が沢山残っていたんですね。
「戦争」ではなく「平和」のための国旗づくりに涙を流した旗屋の社長

札幌冬季オリンピック開会式で入場する日本選手団(1972年)
―― そのようにして苦労されて作った国旗ですが、各国からの承認というのは得なければいけなかったのでしょうか。
はい。各国のNOCに、それぞれ手紙を添えて送りました。国旗のデザインについて各国NOCが国旗の専門家を抱えているわけではないので、yes/noばかりではなく、法的根拠を尋ねたり、具体的な質問をし、変更を希望するならこの布見本から選んでほしいなどと書いたので、結構、長文の手紙になりました。
今のようにEメールがあるわけではなく、航空便でしたから、返事が返ってくるまでには、約3週間かかりましたね。例えばオランダとルクセンブルクの国旗というのは、赤、白、青の「横3色旗」ですが、同じ青でも濃淡が違うわけです。オランダの方が少し濃いんです。ところが、実際にオランダとルクセンブルクの国旗を2つ並べて見比べると、オランダの方が濃いとわかりますが、実際にオランダに行くと、まるでルクセンブルクと同じ空色に近い青を使っている場合もあるんです。また、オーストラリアとニュージーランドからそれぞれ国旗を取り寄せると、デザインは同じような国旗ですが、青の色が微妙に違ったりするんです。そういうものをすべて調整しなければいけなかったので、色見本もつけて送りました。

東京オリンピック開会式で入場するアイルランド選手団(1964年)
―― 調整が最も難航した国はどこでしたか?
アイルランドです。国旗に厳格な人がいまして、やりとりは8回に及びました。アイルランド人というのは、とても神経質な人が多いんです。というのも、イギリスとは全く違う色の国旗ということで、緑、白、オレンジの「縦3色」の国旗にしたわけですが、彼らいわく、3色ともアイルランド人の心に響く色合いがある、と言うんです。でも、それは感覚的なものですから、こちらにしてみれば、そんなこと言われてもわからないわけですよ。そしたら、2つの国旗を送ってきまして、「この2つの中間の色にしてほしい」と。「いやぁ、これは永遠に続くなぁ」とほとほと困りましたね。
今であれば、すぐにアイルランドに出張して、直接やりとりをすれば済む話なのですが、当時はそうはいきませんでしたからね。手紙のやりとりでやるほかなかったんですけども、正直言って、いくら言葉で言われても、なかなか理解が難しかった。ようやくアイルランドから承認を得られたのは、開幕4カ月前のことでした。最後は褒めてもらったので、良かったですけどね。その話は2018年から小学校6年生の「道徳」の教科書(日本文教出版)に私が主人公になって描かれています。
―― やはり、どの国も国旗への執着心というものは強いんでしょうね。
そうですね。いかに各国が自分たちの国旗を大切に思っているかということが判りました。一方、日本はと言えば、私の世代でさえも、国旗に対して愛着というのは諸外国から比べるといささかかけるものがあると思います。私は昭和16(1942)年生まれで、いわゆる「戦争を知らない子ども」の1期生なんです。物心ついた時には、既に日本は「敗戦国」でしたからね。そういう私からすれば、各国の国旗への思いの強さに圧倒されました。
―― 承認を得た後、本番に向けて、大量の国旗が作られていったと思いますが、どのくらいの旗屋さんが関わったのでしょうか?
全部で約3000枚の国旗を用意しなければいけなかったのですが、3つのロットに分けて東京の日本信号旗、大阪の国際信号旗、そして東京旗商工組合が入札で受託し、製造にあたりました。当時、全国に旗屋は167社あって、そのうち今あげた2社が本格的にバンティング(旗布)を使っての製造に慣れていました。どちらも防衛庁の御用達だったので、作り慣れていたといえましょう。しかし、旗屋にしてみれば、ふだんは外国旗というのは、今でもほとんど商売にならないんです。ですから、宣伝旗や暖簾、浴衣、提灯などを作ったりしている人たちが、いきなり外国旗を作るわけですから、こちらが指導しなければならないことも多く、なかなか大変でした。
ただ、オリンピックの国旗を作ることを喜んでくれたところは多かったと思います。例えば、国際信号旗の三宅徳夫社長は当時60代だったと思いますが、私にこう言ったんです。「ついこの間まで戦争のために国旗を作っていた私たちが、オリンピックでは平和のために作ることができる」と。そうして、大粒の涙をこぼされたのです。戦争を知らない20歳過ぎたばかりの若造だった自分には、どう応えていいのか言葉が見つかりませんでしたが、もらい泣きしてしまいました。そして、とうにあの頃の三宅社長の歳を超えた今となってみれば、社長の気持ちが痛いほどわかる気がします。